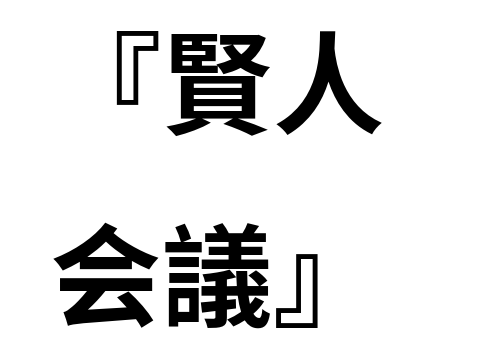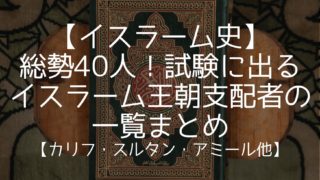『ブラウンシュガー』(短編小説)

下北沢の街をふたりの男が歩いている。
日曜夕刻の下北沢には、「台風に備えよ。」という政府の要請に耳を貸さない多くの若者が集まっている。
黒いマスクをした若い少女の集団が、ガードレールに身体を預けて内側カメラをオンにしたスマートフォンを操ったり、無地のブルゾンを羽織ったバンドマンを意味もなく上目遣いで眺めたりして、自分の帰属感を確かなものにしようと無意識の画策を巡らしている。
ふたりの男はその空気に気圧されるまいとして、いつものどおりの盛況をみせる下北沢の繁華街から、やや足早に離れていく。祝日の月曜を前にした3連休中日の日曜日。街はまだ若い。月曜の午後には大型の台風が都心を直撃するスケジュールになっているからか、若さは今夜のうちに何かを起こそうとしているようだ。
青い煙たさを避けるように静かな路地へ抜けてきた男たちは、どちらもまだ20代前半に見える。一般的にいって若さというものには、愚かさの色と瑞々しさの香りが備わっているものだが、このふたりにはその両方が欠けていた。
だがそれは彼らがもはや若くはないということを必ずしも意味してはいない。
彼らはスマートフォンの内側カメラを使わない。無意識の画策もしない。しかし、やはりこの日曜の夜には、何かを起こそうとしていた。他者との関係にある何かではなく、個人の内部的な何かであった。内部的な何かを引き起こすために街に出ることも、またひとつの若さであるはずなのだ。
「シナモンティーが飲みたい。」
片方の男が言った。この男の名前はブラウンといった。
「いいね、ではママのところに行こうか。先に電話しておこう。」
もう一人も同意した。
彼らには行きつけのブックカフェがあり、木製の二人掛けで交わしてきた言葉の数は、そのカフェの巨大本棚が抱える言葉の数と良い比較になる。
男は軽快な挨拶をした後で電話を切って「シナモンティー準備しといてくれるってさ。」とブラウンに伝えた。電話した男は、名をシュガーといった。
カフェまでは3.4分の道のりがある。方向としては今ふたりがいる住宅街の路地から多少繁華街の方へ戻ることになる。緩く短い坂道を降りて左に折れようというところで、まがり角を形作る一軒家の壁に張り付くように、黒い塊があった。
「シュガー、見てみろよ、ばかデカい猫だ。」
丸々太った大きな猫を指差してブラウンは笑った。
シュガーは多少怪訝な表情をして
「さすがに猫には見えないだろ。」と言った。
「まぁ確かに太り過ぎかもな。どこの猫だろう。」
「気になるなら拾ってあげなよ。」
冗談を言うときは必ずシュガーに繰り返し視線をやりながらニヤニヤと歯を見せるブラウンが、あたかもそれが本当の猫であるように撫で始めたので、シュガーはますます訝しく思った。
「ブラウン、もういいよ。そんな岩。猫には見えないよ。」
それを聞いて今度はブラウンが眉を細めて笑った。
「岩ってなんだよ。」
シュガーも呆れ笑いをしながら返答する。
「いやにしつこいな、岩じゃないか。ママが待っているから早くいこう。」
「なんで岩になるんだ?猫だろう。」
ブラウンの表情は冗談のそれではなかったので、シュガーはとうとうブラウンの頭がおかしくなったかと疑った。
「本当にしつこいな、今日は。岩じゃないか!」と言ってシュガーは岩をコツコツと蹴飛ばした。
それを見たブラウンは焦ってシュガーを止めた。
目を見開いてシュガーを見詰める。
「おい!シュガー、お前正気か?なんで蹴ったりするんだよ。猫、そんなに嫌いだったか?」
ブラウンは猫を庇ってシュガーとの間に入り、責める目つきでシュガーを睨んだ。
ブラウンの胸からはシュガーにも聞こえるほどに怒りの動悸がしていた。
それを見てシュガーは、ブラウンは本当にこの黒い岩を猫だと思っているのではないか、と疑い始めた。
「猫じゃない、岩だろ。」
「ふざけるな。お前にとってはそれくらい興味がないものなのかもしれないが、猫だって生きてるんだ。」
「そんなにムキになって通す冗談じゃないだろ。」
「なんの話だ、冗談でも猫を蹴るなよ。」
ブラウンにはシュガーの行動が解せなかった。
信じたくなかったというほうが正しいかもしれない。
彼らは多くのことを共に語り、意見を戦わせてきた。ときに意見が食い違ったままのこともあった。しかしそれで険悪になることもなかったし、意見を異にするのは同じ大きな思想や道徳感の前提に乗っている、いわば枝葉末節の事柄であった。
猫を蹴るなどいう行動は、彼らがこれまでしてきた議論の遥か下にある、言葉になどするまでもないほど当たり前の前提から、さらに全然落っこちたところにあるものだった。
なぜそんな行動をとって、シュガーはこうも悪びれる様子もない?
まさか本当にシュガーは、これを岩だと思っているのではなかろうか?
そんな疑いとともに、いくつかの深刻な病名が頭をよぎり、ブラウンは恐ろしくなった。
「シュガー、ちょっと確認したいことがあるんだが、いいか?」
「ブラウン、実はおれもだよ。本当の疑問については、その確認の後で改めて問おう。」
「では、前提を作ろう。」
「わかってるよな。」
「「おれたちは画策をしない。」」
「ということは、シュガー。君には本当にこれが岩に見えているんだな?」
「もちろんだ。どうみても岩だ。おれからも聞かせてもらうが、まさかブラウン、君にとってこれは本物の生きた猫だ。」
「もちろん生きた猫じゃないか。からかう気持ちなんてこれっぽちもなくね。」
ふたりはお互いに冗談を言っているわけではないと言うことを確認した。
そして事は思いの外、深刻かもしれないということに気がついたのだった。
数分前にブラウンが見つけたときよりも、気づけば何倍にも存在感を増している黒い塊。
今、この黒い塊は、猫であり、岩なのだ。
「ところでシュガー、明日も早いのに大丈夫なのか?ママのところに行ったらまた夜は長くなるぞ。」
「何を言ってる、明日は休日じゃないか。ブラウンこそ、明日の夜のライブの客引きノルマは達成できたのか?」
「もう台風のせいでライブは中止決定だとさっきも言ったじゃないか。」
「どうやら、頭がおかしくなったわけではないな。」
「試したな。君こそ、一応カレンダーは覚えているみたいだね。」
ふたりは同時に息を吐いた。
「この試し合いは“画策”じゃないのか?」
「相手を操作するためではなく、相手を信じるためになされているという意味において、画策とは言えないよ。」
「また言葉の問題か。同意しよう。」
この後もふたりはその黒い塊の前に留まっていくらか話を続けたが、明白になることといえば、お互いがこの黒い塊についての認識以外のすべてにおいて、いつも通りに至極まともだということだけだった。
「ブラウン、いくらこれが猫だと言っても、これは猫にしてはいくぶん大き過ぎないか?改めて観察してみてくれ。適切に、だ。」
「確かに大きな猫だ。驚くほどにね。でも見てくれ、この柔らかな毛並み、呼吸と共に動く腹、長く揺れる尻尾。これは岩であるというにはあまりに猫すぎる。」
「それがわからない!どうみたって毛はないし、腹も尾も動いていない。そもそも尾など生えてさえいない。それから君、猫という言葉を形容詞として使うのはよした方がいいぞ。」
このふたりはどちらかが正常で、どちらが異常なのだろうか。
黒い塊に関する認識の違いは、それが原因で起きているのか?
そもそも正常と異常という言葉は、何かの性質そのものを表すものではない。これらの言葉が創り出すのは、力をめぐる分断である。
「この世に同じものはない」というグロテスクな事実に立脚し、千差万別種々雑多な存在や事象を、特に際立った共通項で括ってカテゴライズしたのちに、そのなかで特に大きなカテゴリーを「正常」と名付けることで力を与える。社会的な分断の一形態だ。
そして余った小さなカテゴリーには「異常」の名を与えて、力を奪う。
「この世に同じものはない」という奈落のような恐怖から逃れるべく、人間は「正常」と名づけられた枠に自分を押し込めて安心感を得るという不器用な営みを、運命的なまでに継続する。
この営みは、あまりにそれに浸かりすぎると、いずれ「正常」の見えない液体に溶け込んで自分がわからなくなるので、かえって適度な「異常性」に憧憬を抱くというジレンマに陥らざるを得ないという点で、実に不器用である。
しかしこの「正常」「異常」というシールは、カテゴリー同士に大きさの差がない場合は全く機能しない代物だ。
下北沢で黒い塊を前にしたふたりの男。
片方の目にそれは猫と映り、片方の目にそれは岩と映る。
現在、猫と岩の対立には数の大小がない。
この状況では、ふたりは「正常」と「異常」という拙い道具を黒い塊をめぐる対立に適用して安心感を得るべく奮闘するが、結局は、「自分の知覚を信じたい、なぜならそれが自分にとっての真実だからだ。」という原始的な認識論に頼るほかない。
あるものにとって太陽が右に沈み、別のものとってそれは左に沈む。
「西」という絶対概念がなければ、人々は太陽が沈む方角にさえ合意はできない。
では「猫」や「岩」という言葉は絶対概念であると断言できるのだろうか。
それとも「左右」のように主観的な振りかざしが許される、便利な相対概念なのだろうか。
ともかく、下北沢の太陽は、西に沈んだ。
夜の下北沢は表現する。
その表現には必ず画策が混ざっている。
画策の世界から離れ無策な表現を実現しようするこのふたりは、これまで視界を邪魔するシダ植物のように疎ましく思い、可能な限り排除してきた“画策”のその奥には、そもそも何も存在しなかったのかもしれないという疑念を、この黒い塊によって投げかけられて狼狽えている。
曲がり角に留まり、あらゆる角度からの確認作業を互いに繰り出し続けるも、彼らは黒い塊に関する認識以外の異常性を相手に見出すことができなかった。
ふたりの疑いは次第にそれぞれ内側に向かって標的を移していく。
自らを疑うに足る理性を、このふたりは備えていた。
「自分の知覚は真実ではないのかもしれない。なぜならそれが、他者にとっては真実ではないからだ。」
曲がり角で、ある意味でこの日曜の夜の予定通り、「個人の内部的な何か」が起きつつあるのを体感しているふたりの横を、ニーチェが通った。
「話の腰を折るようだけど、あれは哲学先生じゃないか?」
とブラウンがシュガーに言った。
「いや、あれは岩だろう。」とシュガーは答えた。
ブラウンはムムと思ってシュガーを見つめたが、すぐに冗談だと気がついた。
ニヤリとしたシュガーは、
「いや、すまない。あれは確かに哲学先生だ。」と訂正した。
やはり黒い塊に関する認識以外、彼らの間にはズレはない。
「哲学先生!」
ふたりに呼ばれてニーチェは立ち止まった。
「やあやあ、いったい何をしている?」
ニーチェは曲がり角に近づき、ふたりが指差す黒い塊を見やった。
「ブラウンにはこれが猫に見えるのです。」
「シュガーにはこれが岩に見えるのです。」
明らかにふたりが自分の洞察を求めていると察したニーチェは答えた。
「これは三次元空間に存在すると我々に認識されている物体で、可視光線の吸収率が高く、我々が黒と呼ぶものと近い色に見える性質を持っているようだ。」
そういってニーチェは立ち去ろうとした。
「待ってください。結局、猫か岩か、どちらなんです?」
「いま私が言ったことにはふたりとも同意なんだろう?要するにこれは黒い塊だ。君たちの異なる認識には、共通点もあるではないか。分解して考えてみてはいかがかな。もしこれが黒い塊であるという認識にさえ君たち同意できなかったとしたら・・・?恐ろしいね、発狂してしまいそうだよ。」
去っていくニーチェは5メートル歩くと振り返って
「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」
と言うと、ひとつ先の角を曲がって消えていった。
「哲学先生はあのセリフが好きだよね。」とシュガーが言うと
「後世に遺したいと思っているらしいよ。」とブラウンが答えた。
黒い塊に関しての真実を追求していては埒が明かないと判断したふたりは、ひとまずママが待つブックカフェに向かうことにした。
歩いている途中、シュガーはブラウンに向かって
「君にとっての猫を蹴飛ばしたりして悪かった。謝るよ。これからはできるだけもの蹴らないようにしよう。必要な時は、蹴っても構わないものか、相手に確認するよ。」と言った。
「謝ることはないさ、見ているものが違うんだ。おれもこれからは自分にとっての猫が蹴飛ばされたとき、相手が必ずしも猫を蹴っている意識があるわけではないということをよく覚えておこう。」とブラウンは返事をした。
「岩なら蹴ってもいい、というおれたちの会話の前提も、他の誰かにとっては恐ろしい発想かもしれないぞ。」
「いっそ黙ってたたずんでいようか。誰かが勝手にするおれたちへの解釈だけに寄りかかって生きるのさ、あの黒い塊にように。」
「そういう生き方も取り入れるべきかもね。」
細い雑居ビルのエレベーターで5階まで上がると、ママのブックカフェがある。エレベーターの扉が開くといきなりカフェの空間が広がっている。
ふたりが到着するやいなや、シナモンの香りが彼らを迎え入れた。
角にある木製の二人掛けをみると、すでに空のティーカップと、シナモンティーがなみなみに注がれたティーポットが置かれていた。
「すぐ来るっていったのにずいぶんかかったのね。」
ママがふたりに言った。
「ティーポット貸して。温め直してあげる。」
「ありがとう。」
腰かけたふたりは窓から外を眺める。
5階の高さからだとちょっとした眺めだ。
下北沢中の画策が台風前夜の街を巡っている。
明日の夜にはすべてが台風の雨と強風で洗い流されることになっている。
「はい、おまたせ。」
ママが温め直したティーポットをふたりの席に運んできた。
カップに最初の1杯が注ぎ込まれ、その熱を感じた窓が少し白む。
ふたりは考えることもせずに、机の端に置かれた容器からティースプーンひと掬いぶんのブラウンシュガーをカップに入れて、くるくるとかき回した。
ブラウンシュガーが溶けて消える。
微かな甘い香りが漂った。
曲がり角にあった黒い塊は、どこかに消えてしまった。
~語り手による追記~
黒い塊は消え、ブラウンとシュガーの認識の相違問題も雲散霧消となったように思える。認識の違いは、この度は特段大きな争いを生むことはなかった。
ただ、この話にはもうひとつの認識の相違があると、私は主張する。
それは「ニーチェ」についてだ。
「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」というのは間違いなくドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの格言として知られているものだ。晩年に発狂したというのも同じくニーチェに関して知られている史実である。
私がこの物語を綴るうえで、曲がり角を通りかかりブラウンとシュガーに洞察を求められたあの人物を、「ニーチェ」と称した。しかし、ブラウンとシュガーは彼を「哲学先生」と呼び、決して「ニーチェ」とは呼ばなかった。
物語の語り手である私が「ニーチェ」と明言しているにもかかわらず、だ。
物語において語り手は絶対権力者であり、すべてのルールである。しかし、ブラウンとシュガーは私の綴る言語ルールに頑なに抵抗してみせた。
このようなことが続くと物語は混迷し、読者は、語り手と登場人物がそれぞれ何の言葉で何を指そうとしているのかが、判然としなくなってしまう。
ただ、ブラウンもシュガーも悪意を持って他人の言語行動を破壊しようとするような人間では無論ない。そのことは読者の方々も物語を通して感じ取っているはずだ。
ではなぜ、私はあの人物を「ニーチェ」と呼び、彼らは同じ人物を「哲学先生」と呼んだのだろう。
私は、もしかするとここにも例の黒い塊をめぐって起きたのと相似する認識の相違問題があるのではないかと思う。
この仮定が正しければ、物語中でブラウンとシュガーの会話が示唆したように、認識の相違という問題は、黒い塊のような対象物だけではなく、人間のような主体性を持つはずの存在さえも客体化して飲み込んでしまうということになる。
我々は、お互いに認識し、解釈をし合って生きており、そこに事実の介在はないのだ。
そしてその解釈が「岩」のような、ある人にとって取るに足らないものであれば我々は蹴飛ばされ、「猫」のような、ある人にとって愛でる対象たりえるものであれば我々は守られる。
実にあやういことだ。
だから誰しも自らを守るために、正常と異常のまだら模様のうえを必死に泳ぎ、言葉や視線などあらゆる表現を使って画策するのだろう。
では我々には何ができると?
ブラウンとシュガーが導いた答えは、真実の追求を棚上げにして、ただ相手の認識を想像すること。そして、その想像を自分の行動の中に適用していくことであった。
このアイデアには確かに力がある。
すれ違い続ける認識と画策の海で溺れていく私たちを救い上げる確かな力だ。
読者の方々も、いつしか黒い塊に出会うことがあるだろう。
いや、今も毎日のように出会っているはずだ。
それはスーパーマーケットのレジにできた列の中や、テレビ画面に光る映像や、愛する人の瞳の奥に、見えない形で存在している。
存在しない真実にこだわって争いの火種とするのか、相手の認識を想像することで温かいシナモンティーの空間に導くのか。
黒い塊にであったとき、試されているのは私たち自身の問題なのである。