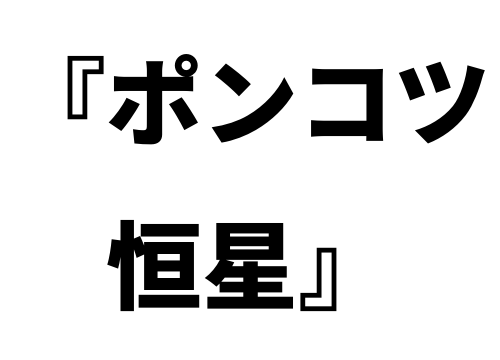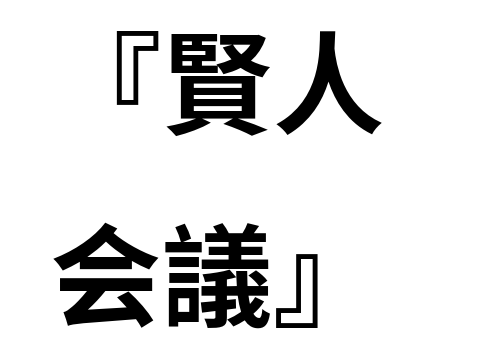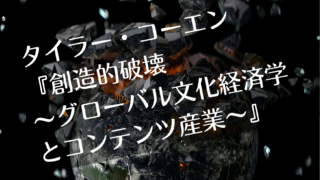大学を1年間休学して世界各国を放浪したことがあった。両親に学費のすべてを出させている小生意気な男であったが、1年くらい稼ぎ始めるのが遅れても何も変わりはしない、実際に自分の目で見て自分の手で触れることでしか学べないことがある、などと一丁前のことを言って得意になっていた。旅費のすべてを自分がアルバイトで稼いだ金で賄ったとう誇るべきではない当たり前のことが、さらに男を得意にさせた。
旅の間は、暇が多かった。外国ではインターネットがない環境で過ごす時間も長く、毎日のように発生する長時間移動でも、本を読むか、流れていく景色を眺めるかしかすることがなかった。暇があると余計なことを考える。余計なことが哲学的に思えてくる。男は旅の道中での出会いや経験を、その膨大な暇な時間の思索の種とした。見知らぬ土地での経験によって、また長い時間をかけた思索によって、男は自分が道徳的な成長を遂げたと錯覚した。具体性を伴わない大切なことが、男の中で大きくなった。その大切なことは客観性もって大切といえると信じた。思索は、「人間」のような大きすぎる分類を主語とする言葉を練り上げることを目的化した。暇つぶしにしては仰々しいものだった。
自分はまだ何もわかっていない、まだ自分が知っていることはほんの一部だ。このような考えを取り込んだことは、男に自身をより俯瞰しているような感覚をもたし、さらに賢くなったような気がした。これは自分の正当性の脆さが見え隠れしたときには保険としても有効だったのだが、男はそんなことは意識に上らせようとしなかった。
長い思索の後で、男は考えることに多くの時間を割きすぎたことに気が付いた。ひとりで考えることは、夢を見ることに似ている。脈絡がなくても、その時はそれが現実のように思える。一方、その脈絡を手繰り寄せることができれば、夢で見たものを現実で再現することも可能になる。また、夢の中で脈絡がどうにも掴みようのないものだとわかったときは、それが夢であることを認知する。男は自分が考えたことについて脈絡を求める必要を感じた。十分に夢を見てから夢を捨てることは、最初から何の夢も見ないことに勝るという理屈を後から練り上げた。
10か月ほどで30余か国を巡り、男は復学した。脈絡を求めるということは、手堅い知識を学ぶことだと結論し、男は学業に精を出した。残りの学生生活では大いに学び、優秀な成績で大学を卒業した。
大した課外活動はしていなかったものの、それなりの学業成績を備えた男は就職活動では苦労しなかった。長い思索の時間の甲斐あってか、学生の多くが就職活動に迫られて初めて向き合う自分の価値観や希望というものは、男の中で既に輪郭が整っているように思われた。自分を繕ったり、ひどい場合は誇張や虚偽をまじえたりした言葉を我が物として流ちょうに操るのは簡単なことではない。しかし男にはこれらの画策はいらなかった。よって自分で自分の言葉を話すだけで済んだ点が、大部分の学生と比較して有利であった。
社会人としての仕事は常に楽とは言えなかったが、決して難しいものでもなかった。男は性格上、極端に頑固や高飛車なわけでもなく、口下手や臆病なほうでもなかったため、上司や同僚からも扱いやすく思われた。男は男で、尊敬できる上司や先輩もでき、順風満帆な生活を送れていると感じていた。徐々に仕事にも慣れ、3年目ともなると自分の責任で動かせる仕事も増えた。自分がこの会社にいる意義を生み出すことができているという感覚は、男の精神生活に安寧をもたらした。生活は平穏だったが長い思索を持つ時間も手堅い知識を蓄える時間も減った。それでも学生時代の思索と知識の蓄積は今も有効なはずで、あのとき自分が道徳的によく優れた位置に昇ったという感覚は残っていた。このような感覚は一見ナルシシズムや独善的な自己認識にもみえる。しかし男のそれは比較的健全かつ、閾値を超えるほど肥大なものではなかったため、これまで周囲の環境や人間関係において悪さを働いたことはなかった。
社会人生活も5年目に入った頃、職場の先輩と2人で地方出張に赴く機会があった。金曜の午後早い時間に仕事が終わったため、そのまま帰路についても良かったのだが、定時後に長時間移動させるのが会社の規則に合わず、土曜朝のチェックアウトでホテルを取っていた。土曜の午前は移動時間として就業扱いになるそうだ。早上がりし、男は先輩の誘いで夕方から居酒屋に入った。男は下戸であるということにしていたため、酒は飲まなかった。出張先には特にこれといった見どころはなかったが、割と有名な競馬場があった。男が競馬をしたことがないという話をすると、先輩はじゃあ行こうと言って男を連れ出した。
先輩は競馬場に入っても酒を入れていたので早々に酔っぱらった。このとき購入した馬券で男は大きく勝った。男の冬のボーナス分ほどの金額が一気に入ってきた。先輩は酔って悪絡みしてくるだけなので馬券が当たっていたことは伏せてタクシーでホテルに帰してしまった。高額の的中馬券とはいえ自動払戻機で換金できる程度の勝額だった。男はその場で現金を受け取った。男は金を何に使うのが最適か考えた。男はあまり物欲があるほうではなく、すでに現在の給与で十分な生活ができていると感じていたため、急に金を渡されてもとりあえず貯金するくらいしか思いつくことがなかった。
ビギナーズラックというやつか、と男は冷静さを保ち、別段舞い上がる様子も見せず駅のほうへと向かった。日はすでに落ちて、駅から自宅へ向かう帰り道の人の波に逆らって歩くことになった。すれ違う人々の表情は、週末が始まる夜とあって、疲れの中に一週間をやり切った清々しさを映しているようだった。2階にある改札口から繋がってロータリーを一周する橋のような空中歩道が広々とした駅だった。(仙台駅のような構造を想像していただきたい。)
駅構内に入る直前の広場のようなスペースでは、街頭募金が行われていた。大学生のアルバイトだろうか。揃いの緑色のジャケットを羽織った男女二人が男に声をかけた。南アジアの途上国の一部の地域で汚水問題が深刻化しており、新生児から5歳ほどになるまでの子どもが汚水による下痢で脱水症状を起こし死亡するケースが絶えないそうだ。しかし、男にはこの募金団体が正当なものなのかわかりかねたうえに、同じく募金をするにも、この世に存在する問題は数知れず、自分がどの問題にために優先的に募金をしたいのか考えなければ判断ができないとも思った。足を止めすぎていらぬ期待をさせてしまうのもよくないと感じた男は、早々に広場を離れた。駅前の輸入食品店で300mlの白のボトルワインだけ購入し、反対口側にあるホテルへと戻った。帰り際、左手にぶら下げていた袋から、競馬で勝った金をすべて口座に入れた。募金というアイデアは男の頭に残った。
先輩とは別のホテルを取っていたので、夜はひとりの時間を持つことができた。私用のノートパソコンを開き、ネットバンキングで口座の残高を確認すると、先ほどの振り込んだ現金分数字が増えていた。男は気まぐれにウェブブラウザで「募金」とだけ入力し検索をかけてみる。半年前からヨーロッパの大国が中東の国家に派兵したことで大きな話題となった紛争地域を支援する国際団体や、先月西日本で発生した大規模な土砂災害の復興支援広告が真っ先に出てきた。しかし、このような注目度の高い出来事についての募金は今回の対象から外すことにした。これは男の考えであるが、まずこのような突発性が高く刺激的な事象には世間の注目が極端に集まるため短期的には多くの資金が集まること。よって男の臨時収入を注ぎ込むのにはさらに適した対象(つまりは深刻であるにも関わらず刺激的ではないか、その問題が存在することに世間が慣れてしまったために注意が向けられず置き去りにされたような問題)があるのではないかと考えた。次に、このような注目度の高い事象においては、その話題が新鮮であればあるほど、それを前面に出した支援団体が乱立し、活動の利害関係が不透明になる懸念があった。要するにホットな話題に便乗する形で支援に乗り出す連中は多くいて、玉石混淆となるためどれが善意によるものでどれが悪意のよるものかは、外部の者には見当もつかない状態になるということだ。厄介なことに、活動している本人は善意で行うものでも、集めた金の送付先には気色の悪い力関係が存在し、それを前提とした利害調整のために金が意図せぬ方向に流れるということがある。
これらの懸念を踏まえて、男は恒常的に存在し、深刻ではあるが刺激性が低いために世間の注目が集まりにくい問題に的を絞ることにした。最終的に白羽の矢が立ったのは、子どもの貧困問題だった。近年はメディアでもよく取り上げられているものの、戦争や災害を動的な問題というならば、こちらは静的ともいうべき性質の問題であるため、注目がムーブメントにつながっていないようだった。複数の団体が見つかったが、どの団体も受け付けているのはマンスリーサポーターのような、少額でも継続的な支援が期待できる形式での寄付だった。男はこの日に手にした数十万円を一挙に寄付してしまうつもりでいたのだが、考えてみればまともな団体ほどそのような寄付の形式を取らないことにも納得がいった。特に子どもの貧困のような静的な問題に関しては。問題の解決には継続的に関心を持ち続けてもらうことが大切だという理由もあるだろうが、支援団体も組織であり、資金を基に計画を立てて動く必要がある。いつどれくらいの額が調達できるのか、予測が立てやすい方法で寄付を募るのも当然だ。
1時間もパソコンをいじっていただろうか。時刻は夜10時を過ぎていた。風呂に上がってから開けたワインも飲み終わってしまった。やや酔いも回ってきたので、金の使い道などの判断はしらふの時にするべきだと判断し、男はパソコンを閉じた。電子版で購入してあった漫画を読んでいるうちに、睡魔がやってきて、男はベッドにもぐりこんだ。
チェックアウトの準備を全くしないで眠りについた男は、翌日起きてから急いで支度を整えた。8時半には駅前から出るバスに乗り新幹線が止まる駅に向かう必要があった。バタバタと準備をして駅に向かうと、バス停にはすでにバスが着いていて、荷物を預ける列に先輩が並んでいた。先輩は、男がギリギリにやってきたことを笑いながら指摘し、バスに乗り込むやいなや、競馬の結果について尋ねた。先輩は昨日タクシーで帰ったことは覚えているものの、細かい会話は忘れているようだった。男は昨日同様、馬券はすべて外れていたと嘘をついた。新幹線の駅についてからは多少時間があった。男が朝食を食べていないということを伝えると、先輩はじゃあ軽食でも食べていくかと言って駅構内にあるカフェに入った。
頼んだサンドイッチが届くと、先輩はここの支払いは俺に任せろと言い出した。実はな、と先輩は続けた。先輩は昨日の馬券で1万円ほど勝っていたらしい。当時は酔っていたため結果を見間違えて外れたと思い込んだが、今朝結果を見直したら当たっていたことに気が付いたのだ。調べてみると当たり馬券の換金は、別の競馬場でも問題ないとのことだった。(当たり馬券を換金前に周りに自慢したいという人がいるそうだ。)だから東京に帰って換金すれば少ないが臨時収入が入るのでここは俺に奢らせろ。それが先輩の言い分だった。
本当は私も当たっていまして。そんな言葉が男の喉元まで出かかったが、なんとか飲み込んだ。まさかあれだけ大きく勝ったとは言えまいし、どうせこれからすべて寄付してなかったことにするのだ。ここで大人しく奢られておくことになんの問題もないだろう。男はそう言い聞かせて、先輩にお礼を言った。男にとって繕って話すことは難しいことだった。繕う必要がない人生を送ってきたからだ。
新幹線では先輩は文庫本を読んでいた。挿絵のあるページを熱心に見ている。窓際に座った男は、ぼんやりと車窓風景を眺めていた。男はふと、昨夜に見た夢のことを思い出した。起きてすぐには覚えていなかった夢の内容が、後になって急に思い出されることよくあった。夢の中で男はクレジットカードの番号を入力していた。支払回数は4回を指定した。一括で払うと上限を超えてしまうからだ。競馬の勝ち分をいっぺんの寄付で受け付けてくれる団体を見つけ、ちょうど支払額と支払方法を入力しているところだった。勝ち分全額を設定し、「支援者として、被支援者向けの資料に名前を記載してもよろしいですか?」のチェックを迷わず外した。男は確定ボタンをクリックした。
ゾク、ゾク。ゾク。男の身体の奥底から得も言われぬ高揚感が沸き上がってきた。間違いなく昨夜の夢で感じたのと同じ快感だ。男は高速で過ぎゆく景色を眺めながらひとりほくそ笑んだ。よく晴れた休日の青空が気持ちよかった。緩む口元を制御できず、窓に近い右腕を持ち上げ、手で口を覆い隠した。この感情は、あの確定ボタンから湧いて出たものだった。誰も知らない。まるで完全犯罪のように利他的な行為を遂行することで、男は自分の善性が立証されたと思った。
男はなぜ昨夜、寄付する先を決めてしまわなかったのか。ワインのせいにしてみたのだが、その建前の裏に男自身も気が付いていない真意がなかったといえるだろうか?まるで数年前に男が「自分はまだ何もわかっていない、まだ自分が知っていることはほんの一部だ。」と言い聞かせて賢い気でいたとき、この考えを自身のための保険として取り入れていたことに気が付きもしなかったように?実際に男は、いっぺんに全額を寄付するという刺激的な行為から生み出される高揚感を夢にまで見た。夢は脈絡を掴めば現実に引っ張り込むことができる。男の笑いは止まらなかった。夢の脈絡は見えている。夢に見た寄付の方式はまだ探せる。夢の再現ではない、本物の高揚感はもはや手に入れたようなものだ。男は初めて体験するこの感情は何と呼ぶのが正しいのだろうなどと考えていた。夢の内容を回想する男の目の前が急に真っ暗になった。
新幹線は長いトンネルに入ったようだ。呼応するように車内の明かりがわずかに強まった。車窓には男の顔が反射して映された。
これほど醜いにやけ顔が今までにあっただろうか。男はこれほど不快なものを見たことがなかった。近くで眺めると胸がイガイガしてくるような不快な表情だ。恍惚としたような瞳と、左手が覆う顔の下半分。瞳の奥にはスンとすました様な余裕の色が見え、まさにゲスの目だった。指の隙間から見える歪んだ口元が帯びる笑みはこの世の何よりも汚らわしいものに見えた。汚らわしい、汚らわしい、汚らわしい。男の胸は瞬く間にそんな感情で満たされつつあった。しかし窓に映る顔は少しも変化せず、下卑た表情を浮かべている。その表情に善性はなかった。たとえ天地がひっくり返ろうとも、その表情に善性はなかった。
男は張り付いたようなその顔に狼狽しながら、横で文庫本を眺める先輩はどれだけ善に溢れていたかと考えた。男は窓に映る下卑から目を離すことができなかった。時速200km以上で走る車両は、いつまで経ってもトンネルを抜けることはなく、男は自分の中から出てきた化け物染みた何かと、永遠のように向き合うこととなった。隠れていたもの、見えないはずだったものが見えてしまうことがこれほど恐ろしいとは想像もしなかった。「自分はまだ何もわかっていない、まだ自分が知っていることはほんの一部だ。」という言葉が思い返された。これは形式的に使われていたに過ぎないだけでなく、自分という目的語を適用したことがなかったという点でまがい物だった。知らない自分がニタニタと笑い続けていたが、自分であるということはどうにも否定できなかった。もう耐えられないと思った男は、両手で顔を覆ってしまったが、例の表情は瞼の裏にも張り付いているようで、逃れることはできなかった。
夢にまで見たあのゾク、ゾク。ゾク。という高揚感。その脈絡は確定ボタンではない。その脈絡は、この下卑た表情を浮かべた、自分の知らない自分であった。この本性。自分でも本当に知らなかったのか、見ないふりをしてきただけなのか、もはやわからないこの本性。これが男の高揚感の脈絡である。男は考える。自分ではかけがえのない経験だと思っていたあの旅も、自分の価値観を固めてくれたと思っていたあの思索も、自分を成長させてくれたと思っていたあの勉学も、自分の言葉で喋っていると思っていたあの問答も、周囲とうまくやっていけると思っていたあの性格も、それなりに徳を備える自分が値するに相応しいと思っていた生活の安寧も、取り繕う必要などとなかったと信じてきた生き様も、すべて勘違いだったのではないか。今でも制御不能に湧き出てくるゾク、ゾク。ゾク。この高揚感を何と呼ぶかは結局わからずじまいになりそうだが、この高揚感を感じる精神のことはこう呼ぼう。下卑。男は自分の下卑を初めて知ったのである。止まらない高揚感。男の理性と感情はこれを拒絶しているが、男には届かない奥底に眠る本質の下卑を殺さない限りこれは止まらない。下卑を殺すことは可能だろうか?自分もろとも殺す以外の方法で?しかし、男は下卑を見た。自分の下卑を見てその存在を認識することが、下卑を殺すための前提条件である。下卑との対峙で精いっぱいとなっている男には、その小さな一歩を踏み足していたことに気付く余裕はなかった。
パッと視界が一斉に晴れた。長いトンネルを抜けたようだった。下卑は消えて、また青空が広がった。無意識に呼吸を止めていた男は、あー、と息を吐いた。左に座る先輩に目をやると、まだ挿絵の載っているページを開いていた。下卑の圧倒からは逃れたが、下卑がここにいることは理解してしまった。そう思えば、これまでのあらゆる行動や感情や思想が、下卑を動力源としたシステムのうえで動いていたようだ。下卑を殺さなければならない。そう思う心自体が、男の奥底で下卑と並んで存在する善性だったが、男にはまだわからなかった。それを男が認識したときに、善性は下卑に上書きされてしまうのかもしれない。
「先輩。」
「ん、何?」
「実は僕、下戸じゃないんですよね。」
「え、そうなの?」
「はい。飲めるんですけど、会社で飲めることにすると誘われたりして面倒くさいので嘘ついていました。」
「まじかよ。あーでも、そういうのもアリなんじゃないか?時代も時代だし、もう飲みニケーションとかダサいみたいな感覚あるでしょ。20代は。てか、なんでいま急にカミングアウトしたんだよ。」
「あと、昨日の馬券、僕めっちゃ勝ってました、実は。でも黙って朝食奢られました。すみませんでした。」
「は!?まじ?いくら勝ったの?」
「ボーナス1回分くらい。」
「えー!すげえ超勝ってるじゃん!いや、待てよ。さすがに嘘ついているだろ。急に下戸じゃないとかもおかしいわ。俺お前が飲んでるのマジで見たことないし。」
「んー。一応昨日もホテル返ってからワイン空けてるんですよ。あ、レシートありましたよホラ。」
「え、じゃあ競馬勝ったのも本当?」
「だから本当ですって。」
「お前、嘘つき野郎だったのか。」
「すみませんでした。」
「はは、真に受けるなよ。それだけ勝つと言いにくい感じわかるし。ちなみに、勝った金何に使うの?」
「まだわかりません。急に大金もらっても特に欲しいものもなかったですし。」
「うわー。最近の若者~。俺ならそれだけもらっても足りないくらいだな。欲しい車も買えない。」
「とりあえず東京着いたら焼肉でもいきます?全部出しますよ。先輩に言われて買った馬券ですし。」
「お!昼から行っちゃう?お前もうゲロったんだから飲めよ。」
「はい、もちろんです。飲みましょう。」
「冗談冗談、後輩に奢られる先輩がどこにいるんだよ。あと今日は午後から息子を出かけに連れていくって言っちゃってるんだわ。めったに当たるもんじゃないんだし、自分のためにちゃんと使いな。」
東京駅に着き、先輩と別れ、男は在来線に乗り換えた。トンネルに入った時に車窓に映る自分の表情を見たが、下卑は影を潜めていた。しかし、先輩が焼肉を断ったとき、在来線の改札で出てくる人とかち合ったとき、この車両に乗ってすぐ赤ん坊を抱いた女性に席を譲ったとき、男は下卑の存在を確かに感じた。下卑は目に見えない。下卑が存在することと、下卑が間接的に表出するとき目に見えるものが実際に下卑た行動であるかどうかとは、何の関係もない。男が風で倒れた飲食店の立て看板を直すとき、底に下卑がある。男がやるべきことを後回しにソファに寝転がってスマートフォンで動画を観ているとき、底に下卑はない。そういうものだ。
競馬の勝ち分をどうするかという問題は解決していない。男は下卑を避けて金を寄付する方法を考えていたが、何も思いつかないまま家についてしまった。いきなり夏日になったので、移動してきただけなのに汗をかいていた。手短にシャワーを浴びて、出張中に溜まった洗濯物を回した。ドラム式の中で回る洗濯物を見ていると、扉にまた自分の顔が映っていた。
着替えを済まし、デスクトップパソコンを立ち上げ、昨夜にあたりを付けていた団体を再度調べてみた。やはりいっぺんに多額の寄付を受け付けるページは見つからなかった。男は団体に電話をかけ、寄付したいという意思を伝えてみた。大変喜ばれたが、口座振込になるか、別の方法があるか、担当に掛け合って確認が必要だと言われたため、折り返しの番号だけ伝えて電話を切った。電話口の女の声色が感動に染まった瞬間、ゾク、という音が聞こえた気がしたが、男が「下卑!」と意識するとすぐに収まった。下卑を認識すると、下卑は下卑ではなくなるのかもしれないという仮説が立った。
再び電話が鳴るまで、男はソファに横になり目をつむった。自分の中にある下卑の存在を、素直に認めることができただけ、自分はマシな人間かもしれないという慰めが心をよぎった。下卑の存在と向き合っても、下卑を認めない人間も多いはず…、とその瞬間、口元が僅かにほころんだことに気が付いた。男は、こういうところか、と、そう簡単に何かが変わるはずもないと思いなおした。