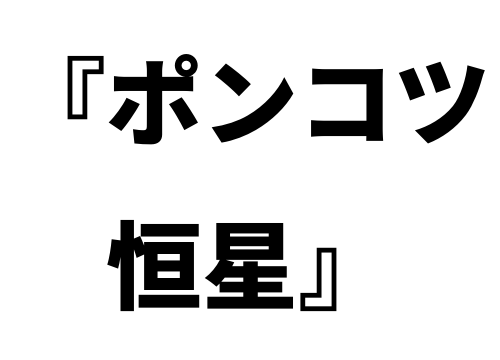人間の歴史には、人々が感覚的な共同体として生きている時代が長くあった。当時は国という概念もなく、住所や戸籍もなかった。私たちは、この大地がどこまで続いていて、この先に誰がいるのか、何も知らなかった。学問や図書館はもちろん存在せず、知識と言うのは、先人から慣習的に口伝されてきたものと、私たち自身の目で直接見たものだけだった。丘を越えた向こうから、突然別の人間がやってくることもあったし、こちらから誰かしらがふと丘の向こうに消えていくこともあった。出会いと別れは日常であり、ロマンティックなものでもセンチメンタルなものでもなかった。それでも流動する人間たちと支え合ったのもまた、人間たちだった。
老人は湖にいた。もっさりと蓄えた髭は白く染まり、目じりや頬のしわは深くなり始めていた。年齢は50代後半ほどだろうか。当時としては長生きしているほうで、老人と呼んで差し支えない齢だ。この土地には豊富な食物がある。若い働き盛りの衆が数時間も狩りをすれば、その数倍の人口を支えるだけの食べ物が容易に手に入ったし、少年たちが林に入って遊びの片手間に獲得する木の実や果物だけでも、生命を維持するにはなんとか事足りるくらいだった。このときはまだ生産経済が発達しておらず、食物を貯蔵するという発想や技術も生まれていなかったが、食事時にその場に顔を出しさえすれば、誰でも食事にありつくことができた。老人も例にもれず、その土地の豊かさに浴した生活しており、食べるに困ったことはなかった。
この日に湖にいたのもほんの暇つぶしのようなものだった。魚を釣る道具を持ってきてはいたが、漫然と糸を垂らしてぼんやりしているだけだった。向こう側には数キロ先まで見通せる原地が広がっていて、その先に微かに林が見える。林の背景には標高700メートルほどの山が連なっており、このような平地では低山でもよく目立つ。太陽は毎日この連山の後ろから現れるため、人々は連山に対して種の信仰のようなものを持ち始めていた。この日も太陽は山の上に浮かび、それが稜線から少しずつ離れていく様を、大きな岩の上に腰掛けた老人はただ眺めていた。釣り竿はピクリとも動かなかった。その気になるなら、その辺に転がっている石をひっくり返してミミズでも取れば、釣りの餌にして魚を釣りやすくできたかもしれない。しかし、老人は浅瀬に見えている貝にさえ何の関心を示さない有様だった。
「何やっているの?」
老人の背後から声が聞こえた。振り返ると若い少年が立っていた。12~14歳くらいにみえる。当時ではすでに大人として扱われる年齢に差し掛かっていたが、あどけなさが残る年齢でもある。
「釣りだよ。見たらわかるだろう。」
老人は水面に向き直りながら答えた。
「釣りって何さ。」
「なに、釣りを知らん?言い方が違うのかな。魚を取っているんだ。」
少年は老人が座っている岩によじ登ってきて言った。
「ああ、ポヤか。そんなやり方でポヤがうまくいくの?」
少年も老人にならって水面を見下ろした。魚が泳いでいるのがときおり目視さえされたが、釣り針に食いつく気配はなかった。
「君は丘の向こうから来たのかい?」
「丘?丘ってどの丘のこと?」
「この辺で丘と言ったら、あの丘のことさ。」
老人は後ろを振り返って背後にある丘を指さして言った。
「違う。僕はあの山の向こうから来たんだ。」
少年は老人とは正反対の方角、つまり老人が太陽の昇るのを見届けていたあの連山のさらにの向こうを指さして言った。太陽はまた上に昇っていた。あと数時間で南中するだろう。
「驚いた。『旧い土地』から来たのか。初めてだよ、そういう人にあったのは。」
人々の間には太陽をはじめとする天空の動きと時間に関わりがあるということがわかっていて、山の向こうから押し出されてくる天空と、同じ方角から流れてくる小さい川のせいで、「山の向こうのほうが時間的に昔なのだ」というぼんやりとして認識が生まれ始めていた。それで、山の向こうを自分たちの故郷に見立てて「旧い土地」と呼ぶようになった。
「『旧い土地』?ここでは山の向こうをそう呼ぶんだね。僕たちは『コムフェの横』って呼ぶよ。」
「なんの横だって?」
少年は岩から岸に飛び降りた。湖の水面に手を付けて水をすくった。
「コムフェだよ。これは小さい水だろ。しかも、塩っ辛くない。」
水を飲み、腕で口を拭いながら少年は続ける。
「でもコムフェはこれよりずっとずっと大きい水なんだ。木で作ったコマフムっていう乗り物で浮かぶこともできる。コムフェの水は良く浮くからね。あと味もすごく塩っ辛いんだ。飲めたもんじゃないよ。」
少年が話しているのは海のことだ、と老人は気がついた。彼もずっと昔に海の近くに居付いていたことがあった。それは少年が来た旧い土地とは全く異なる方角にあったのだが、確かに海だった。
「コムフェか。きっと私もそれを知っているよ。海って呼んでいたんだが、きっと君のいうコムフェと同じだ。コマフムにも乗ったことがある。船という。もうずいぶんと前のことだが、連中の間で噂になったんだ。コムフェはいろんなところにあるが、実はすべて繋がっているんじゃないか、ってなあ。どこでも塩っ辛くて、川や湖の水とは全然違うだろう?それで、私がコマフムに乗ったのは岸から見える島にいったときだったんだがね。そのときみんなで考えたんだ。コムフェに囲まれた島があるなら、私たちがいるこの土地も、実はすべてがひとつのコムフェに囲まれた島なんじゃないか・・・って。それならすべてのコムフェが本当はひとつに繋がっているとしてもおかしくない。味がすべて同じく塩っ辛いのも・・・おかしくない。」
少年はきょとんとした表情で老人を見つめていた。
「何言っているのさ。コムフェがひとつなんて、あたりまえじゃないの。」
そうか、その少年はこれまでひとつの海しか見たことがないのだ、と老人は思った。彼はまだ10年とちょっとしか生きておらず、きっと旧い土地から出てきたのも今が初めてなのだろう。だから、複数の海を知っている私たちにとって、すべての海がひとつなぎであるという考えがどれほど果敢な発想であるか、想像ができないのだ、と。
「旧い土地の人たちは、みんなコムフェは当然ひとつだと考えているのかい?」
「そりゃそうさ。コムフェがたくさんあったら『コムフェの横』もたくさんなくっちゃおかしいでしょう。『コムフェの横』がひとつなんだから、コムフェをひとつだよ。」
老人は少年の言い分に全然納得できなかったが、世界は人間の尺度で測ることができるものではないと直観的に理解していたので、すぐに考えるのをやめた。少年も、世界をあるがままに見るだけで、それに解釈を与えようという気はまだなかった。
「君はどうしてこちらにやってきたんだ?」
老人は少年に尋ねた。
「僕は何だと思う?」と少年は尋ね返した。
老人の質問はなんとなく間を持たせるためにしただけのもので、当時は何の理由もなく人が移動することはよくあったため、大した答えを期待したものではなかった。反対に、少年の質問には真理への探究心のような、純粋な精神が込められていた。
少年は浅瀬にある貝を拾い始めた。多くは2枚貝であり、なんとかこじ開けようとする少年とそれをさせまいと粘る貝の静かな戦いが始まっていた。
「貝が何か知るには、貝の殻を開けてやればいいんだ。」と少年は言った。
「じゃあ君が何者かを知るには君を切り開いてやればいいんじゃないか?」と老人はニヤつきながら答えた。
「僕を切り開いたら、そこに僕の正体があると思う?」
どうやら面倒な奴が来たな、と老人は思った。
「ないだろうな。」
ちょっと黙ってから老人は続けた。
「貝だって殻を見るだけでも何かはわかるぜ。」
「それもそうだね。」と少年は答えた。
「じゃあ、僕を見るだけでも僕が何かはわかるよね。僕は何だと思う?」
少年は最初の質問に戻った。会話の最中も少年は貝を拾い続けていて、拾った貝は岸に二山に分けて集めていた。
「君は、そうだな。旧い土地から来た男の子だよ。」
「コムフェの横だってば。」
「そうだった。コムフェの横の男の子だ。」
「コムフェの横には僕以外にもたくさん男の子はいるよ。」
「じゃあやっぱり旧い土地から来た男の子だ。旧い土地から来た男の子は君が始めてなんだから。」
「それならコムフェの横では、今頃僕は『逆の川の大地に行った男の子』になってるはずだね。」
「逆の川の大地?」
「コムフェの横ではこっちのことをそう呼ぶんだ。」
少年は貝殻を岩にぶつけて割るのを中断して、例の山々を指さした。
「あの山からは川が流れているんだ。こちら側に向かうものと、コムフェの方に向かうものが両方ある。コムフェの横にあるほうが『川』だから、こっちの川は『逆の川』。ここは『逆の川の大地』。これも、こっちでは別の呼び方がある?」
老人はしばらく考えてから答えた。
「いいや。ここはここだよ。ここにいるんだから、『ここ』でいいじゃないか。」
「でももし別のところに移動したら?あなたも昔は別のところに居たんでしょう?それじゃあ『ここ』が変わっちゃう。」
老人は頭が痛くなってきた。ここはここでよくて、それで困ったことなど一度もなかった。どうして少年がそんなことにこだわっているのか全然理解できなかった。老人は久しぶりに竿を引き上げてみた。何も釣れてはいなかった。貝を割り終えた少年が貝の身を持ってまた岩に登ってきた。
「こうやってポヤをするんだ。」
少年は老人の釣り針に、殻を勝ち割って採取した貝の身を付けながら言った。
「これに魚が食いつく。何て言ったって、殻を割る手間はこっちで済ませてやったんだから。貝はたくさんとったからね。ちょっとくらい失敗しても大丈夫だよ。」
割らないで取っておいた方の山は、そのまま貝として食べるために残しておくそうだ。
その間も老人は少年の質問にどう答えたものかと考えていた。「ここ」が変わってしまったらどうしていけないのだろうか。「逆の川の大地」だって、こちらからみたら逆ではないじゃないか、「こっちの川の大地」じゃないか、という不満もあった。
「『ここ』が変わってもいいんじゃないか?『ここ』が変わってから『ここ』には別の言い方を考えるよ。」
「どういうこと?」と少年は問い返し、老人も自分で言っていることがよくわからない気がしてきた。もしかしたら少年の言うとおり、「ここ」が変わったら困るのかもしれない。黙ってしまった老人の心を読んだように少年が続けた。
「ほらね、やっぱり『ここ』が変わっちゃうのはおかしいんだ。だから僕がこっちでは『旧い土地から来た男の子』で、コムフェの横では『逆の川の大地に行った男の子』になっちゃうのも、やっぱりおかしいんだよ。」
その時、釣り竿がブルルと動いた。魚が食いついたらしい。老人が急いで竿をあげると大きな魚が釣れた。腹がピンク色に染まった、鮮やかな魚だった。これはうまいやつだぞ、と老人は喜んだ。
「おい、ほら見てみろ。やったぞ!」と老人は手柄を少年に見せつけた。釣れようが釣れまいがどうせ食べ物にはありつけると思ってダラダラと釣りをすることに慣れて、いつの間に忘れてしまっていた喜びだった。
「僕のおかげだね。」と少年は言った。
「釣ったのは私さ。」と老人は言い返した。何かにムキになるというには久しぶりだった。太陽が南中していた。
釣ったのは私さ。という自分の言葉が老人の中で反響した。今自分はムキになっていたぞ、と。そうだ、今自分はムキになって、自分の手柄を見てくれと思ったんだ、と。老人は思考するということに慣れていなかったため、自分の頭の中で何がわかったのか言葉で整理することが出来なかったが、直感的には確かに気づいていた。それを説明するならば、先の『ここ』『旧い土地から来た男の子』『逆の川の大地に行った男の子』などは、どの表現をとっても、言う人の視点で対象が語られているということに対する違和感だった。だから言う人が移動したり、別の人が言ったりするときには、言葉が指すものが変わってしまう。それをさけるなら表現を変えないといけなくなるのだ。少年はそれを困ると言っているのだ。このような内容がぼんやりとした直感として老人の中に生まれたのだった。
少年はきっと自分が自分として語られる言葉を探しているのではないか。老人が「釣ったのは私さ。」と言ったときに、他でもない自分の実績を見ろという気持ちが無意識に沸き上がってきたように。
「わかったぞ。確かに釣れたのは君のおかげだ。それで君が何かがわかった。最初の質問だよ。君は『ポヤがうまい男の子』だ!」
どうだ、という自信に満ちた表情だった。少年も口角を微かに上向かせた。しかし、一瞬あごに手を当てて考えたあと、再びあの純粋な精神を湛えた瞳を老人に向けてこう言った。
「うん。わからないけど、さっきよりも僕に近い気がする。確かに近いよ。でも、まだダメだよ。ポヤがうまい人は他にもいるし、男の子も他にもいる。僕よりポヤをうまくやる人がいたら僕はもうポヤがうまい男の子じゃなくなっちゃう。それにね・・・えーとポヤは、『ここ』、つまり『逆の川の大地』では、ポヤのことをなんて言うんだっけ。」
「釣りだよ。」得意顔を不満顔に変えた老人が短く答えた。
「そう。釣り。僕は『ここ』では『釣りがうまい男の子』になっちゃうね。コムフェの横では『ポヤがうまい男の子』なのに。それも困るんだよ。僕がそんなに簡単にポンポンと変わっちゃあね。」
老人は自分の気づいたことが即座に否定されたのが悔しかったが、すでに少年が困っている内容を理解して始めていたので、少年の反論にはぐうの音も出なかった。ただ、少年も認めているとおり、少年自身を言葉で描き出そうとする老人の姿勢は、正しい方向を向いているようである。
「火でも起こそう。こいつはきっとうまいぞ。」
老人は気を取り直すように言うと、ゆっくり岩から降りてきた。
「おじさんは何なの?」と少年は尋ねた。
「ちょうどそれを考え始めたところだよ。」と老人は火起こしに取りかかりながら答えた。自分は何であるのか。彼は今までそんな疑問を持ったこともなかった。旧い土地の人々は変なことを考えるものだと思ったが、だんだんとこの疑問に興味を惹かれているような気もした。
「旧い土地、いや、『コムフェの横』では、みんなこんなことを考えるのかい?」
「まさか。誰もこんなことは考えないよ。誰も考えないから、僕はこっちに来てみているんだ。こっちでダメならあっちにも行く。」と少年は例の丘の向こうを指さした。
「あっちはダメさ。私たちとあの丘の向こうでは、人がよく行き来する。向こうに行ったきりの奴もいるし、こっちに来たそのまま居ついたのもたくさんいるんだ。だが、誰も君みたいな質問はしてこない。」
炎が付いた。釣れた魚を焼き、貝を煮る。どうやら太陽を生み出すように見えるあの山々の向こうにも、生きているのはこちらのいるのと同じ人間らしい。このことを人々が知れば、連山に対する畏敬は残るにしろ、にわかに形成されつつある信仰のようなものは有耶無耶に霧消していくのかもしれない。少なくともこの老人にとって、山の向こうはもはやそれほど特別なものではなくなりつつあり、代わりに少年の発する問いが特別なものに思えていた。
「魚が焼けた。貝も煮えた。さあ食おう。」と老人がいつのまに岩の上の戻っていた少年を見やると、さらにもう1匹魚を釣り上げたところだった。老人にとって、自分が取ったもので他人と食事を囲うのはずいぶん久しぶりだった。
「旧い土地では、いや、『コムフェの横』では太陽はどこからやってくるんだ?」
「もちろんコムフェからだよ、コムフェはすべての源なんだ。太陽も食べ物も、空気や時間だって、全部がコムフェからやってくるのさ。そしてあの山からコムフェに向かって川が流れているってさっき言っただろう?それが唯一コムフェへ向かっていくものなんだ。きっとコムフェからやってきたものは、すべてあの川からコムフェに帰っていくんだよ。」
海から太陽が昇るという風景は、老人は全く想像ができなかった。
「いつか見てみたいものだね。あの山を越えて旧い土地まで行く体力はもうないが。いや、いつもは釣れなかった魚が今日は2匹も釣れたんだ。ムキになれば行けるかも知れないな、コムフェの横まで。」
「ねえ、僕らの間ではさ、僕の土地のことは『コムフェの地』って呼ぶことにしない?『旧い土地』と『コムフェの横』を合わせてさ。両方混ぜて話されるとわかりにくいんだ。」
「それもそうだな。」
少年の言うことはもっともだったので老人も同意した。思えばポヤだのコムフェだのという言葉も、老人が少年の呼び方に合わせて統一していたのだった。
ここで起こった名づけという行為は、老人に歴史的に重要な閃きを与えた。目を見開いた老人は周囲をグルリと見渡した。目に映るすべてものが今までとはどこか違って見える。つまり、それが何であるか、全く確かなものと、まるで不確かなものと、その間でぼんやりとしているものがあったのだ。
「そうだ。今度こそわかったぞ!」と老人は少年に向けて叫んだ。頬張っていた魚をグイと飲み込んだ。
「君が何かわかったんだ。そうだ、君はまだ君でしかない。あたりまえだ。君は君でここにいるのが本物に決まっているじゃないか。でも君に『僕は何だと思う?』なんて聞かれると困ってしまった。それはね、君を君じゃないもので説明しようとしていたからなんだよ!わかるだろう?」
少年は老人がなぜこうも興奮しているのが解せなかったが、大人しく話を聞いていた。
「うん。でも、何かをそれじゃないもので説明するなんてあたりまえじゃないか。『コムフェの横』はコムフェの横にあるから『コムフェの横』なんだ。『逆の川の大地』も、逆の川が流れていく大地だから『逆の川の大地』ってことだ。」
「違うんだよ。そうじゃないんだ。じゃあ『コムフェ』は?『コマフム』は?『ポヤ』は?別に何かそれ以外のもので説明しているわけじゃない。コムフェはコムフェだろう?」
少年はまだ老人の意が掴めない。
「そうだよ。だから何っていうの。」
「さっき君は、こう言った。『僕らの間ではさ、僕の土地のことは『コムフェの地』って呼ぶことにしない?』って。つまりだよ、私たちの間でこれから『コムフェの地』って言ったらいつも君の土地のことだ。たとえ他のコムフェがあって、その横に土地があったとしてもね!」
「コムフェはひとつしかないよ。」
「コムフェは他にもあるんだ!ああ、いや。コムフェはもしかしたらひとつに繋がっているかもしれないとは思っているんだが・・・コムフェの横とかコムフェの地とか言えそうな場所は、『コムフェの地』以外にも確かに・・・ああ!今はよいとしよう、そんなことは!コムフェを使って話すからわからないんだ。そうだな、例えばあそこに丘があるね。さっき私はこの辺で丘と言ったらアレのことだと言った。でもな、他にも確かに丘はある。だから君みたいな別の土地から来たばかりの人には丘といってもどの丘のことかわからないだろう?それで例えば、あの丘のことは、そうだな、『夕日ヶ丘』って呼ぶことにするんだ。私たちの間でさっき君の土地を『コムフェの地』って呼ぶことにしたのと同じことさ。それを君と私の間だけじゃない、みんなの間で決めるんだ。」
「じゃあ、例えば、『逆の川の大地には、夕日ヶ丘の向こうからたびたび人がやってくる』とか、そういう風に言うってこと?」
「そのとおりだ。」
「まあ、それでもいいよ。」
少年は老人の話の意味は理解したが、それが何故最初の質問「僕は何だと思う?」と関係があるのだろうと思った。
「チスカ。」
老人が少年を見つめて言った。少年は戸惑った。
「最初の質問をもう一度してくれ。」
老人がそういうので少年はよくわからないままに最初の質問を繰り返した。
「僕は何だと思う?」
老人は満足そうに頷いて、ゆっくりはっきりと質問に答えた。
「君は、チスカだ。」
「どういうこと?」と少年は返した。老人はよくぞ聞いてくれたという風に答え始めた。
「君の土地は『コムフェの地』だ。あの丘は『夕日丘』だ。そして君は『チスカ』だ。僕たちがさっき決めたのは場所の呼び方だが、同じように君の呼び方を決めていけない理由はないじゃないか!君はチスカで、チスカといったら君のことなんだ。これはどんな場所に行っても変わらない。誰が君を呼ぶにしても変わらない。君はいつもチスカなんだよ。ほら、チスカ。君が釣った魚も焼けたぞ。」
老人はそう言って、魚を少年に手渡そうとした。少年は魚には目もくれずに両の掌を広げて見つめていた。
「チスカ・・・。僕は何かっていったら、僕はチスカなのか。そうか、これでどこにいっても僕はチスカでいられるんだね。」
知りたかった答えが見つかったのかしれないという感覚がじわじわと湧いてきて、彼の声を少しずつ確信に満ちていった。
「そうだ、君はチスカだ。切り開くまでもない。わかりきったことだ。君は君でここにいて、その全部がチスカなんだ。」
「でもどうしてチスカなの?」少年はやっと受け取った魚をかじりながら聞いた。
「知ったことかい。ただ君の顔を見ていたら思いついたんだ。気に入らないなら別のを一緒に考えるとしよう。」
「ううん、チスカがいいよ。チースに似ていていい感じだ。」とチスカは言った。
「チースってなんだい?」
「チースはチースだよ。ほら空気が気持ちよくこうやって流れて、ときどきビュンとなるじゃない。」とチスカは身振り手振りしながら答えた。
「風のことか。風のことをコムフェの地ではチースというのか。」
「ねえ、また聞いちゃって悪いんだけどさ。おじさんは何なの?」とチスカが尋ねた。
老人は答えあぐねてしまった。そうか、私も困ったことになった。チスカを前にすると自分がひどくぼやけたものに思えてきたぞ、と。
「困ったぞ。わからない。」と老人は言った。すると今度はチスカが得意げになって
「おじさんは、ミーシュカだ。」と言った。
「なんだって?」
「ミーシュカ。おじさんはこれから、いつでもどこでも、誰にとっても、ミーシュカだよ。」
「どうしてミーシュカなんだ?」と老人が尋ねた。
「僕はチースのチスカだ。だからおじさんはミーシのミーシュカさ。チースの中を羽ばたくのはミーシだ。良い組み合わせでしょう?」
ミーシというのはきっと鳥のことだな、とミーシュカは思った。
「あとはね、ポヤがもう少しだけうまくなりますようにって。ミーシを見習ってね。」とチスカがいたずらっ子のように付け足した。やっぱりミーシは鳥のことだ、とミーシュカは思った。鳥は魚取りがうまい。ポヤは釣りだけでなく魚を捕ることは全部ポヤなのかもしれない。気が付けば太陽は夕日ヶ丘に近づいて赤く染まっていた。チスカとミーシュカは食事を終えて、コムフェは本当にひとつであるかという問題について、ゆっくりと話し合った。
太陽が、コムフェの地を背後に抱えるサヘレ連山から顔を出した。ミーシュカがチスカに聞いたところによると、サヘレはコムフェの地の言葉で太陽という意味だそうだ。ミーシュカが、夕日が沈む丘を夕日ヶ丘と名付けたので、チスカもその連山をコムフェの地の言葉で同じように呼ぼうとした。しかし連山はコムフェの地から見ると夕日が沈む場所だが、ミーシュカの土地から見れば朝日が昇る場所である。ここでちょっとした言い争いが起こり、最終的にはどちらも太陽であるには変わりないということで、太陽を表すサヘレを名に冠すことになった。
この日もミーシュカは湖にいた。残りの人生は長くない。きっと人生の長さをサヘレの軌道に例えるなら、もう夕日ヶ丘にその端が触れ始めていることだろう。昨日ミーシュカは魚を16匹釣り上げた。これは今までの最高記録だった。チスカに倣って貝を餌に釣りをするようになったのだが、特に魚の食いつきが良い種類の貝がわかるようになってからは目に見えて成果が上がるようになった。誰でも食べるには困っていないのだが、それでもミーシュカが食事時にたくさんの魚を持って現れるとみんなが喜んだ。もうポヤの腕はミーシにも負けないはずだ。名前に負けないミーシュカになったぞ、と彼はそれを誇らしく思った。チスカは肉体的にも完全に大人になり、有り余る体力を持ってまさに風のようにサヘレ連山を越えてコムフェの地とミーシュカの土地を行き来している。あとサヘレが10回も沈めばまたこちらにヒョイと戻ってくるだろう。次にチスカがコムフェの地に向かうときは、ミーシュカもついていって、コムフェから昇るというサヘレの姿を拝みにいこうと考えている。きっとそれが最後のチャンスになる。風の力を借りて空高く飛ぶ鳥のように、ミーシュカはチスカと共に山を越えたいのだった。山の向こうは別の土地だが、どこに行ってもチスカはチスカであり、ミーシュカはミーシュカであるという確信が彼ら自由にしているようだった。
人間の歴史には、人々が感覚的な共同体として生きている時代が長くあった。当時は国という概念もなく、住所や戸籍もなかった。しかし、名前という概念はそれらよりも一足早く生まれていたという。丘を越えた向こうから、突然別の人間がやってくることもあったし、こちらから誰かしらがふと丘の向こうに消えていくこともあった。出会いと別れは日常であったが、名前を知り合った人間同士の間では、ロマンティックな気持ちやセンチメンタルな感情を呼び起こすものになりつつあった。流動する人間たちと支え合ったのもまた人間たちだった。そのような流動は人やモノや場所に与えられた名前によって、徐々に徐々に、私たちの時間間隔からすればひどく緩慢な速度で、それでも確かに秩序化されていった。長い歳月のなかで歴史は感覚的な共同体の時代を抜け出し、新しい時代への移り変わるのだった。