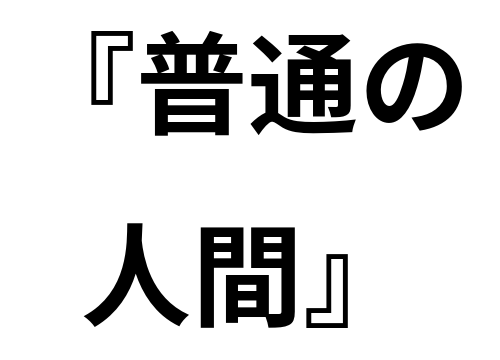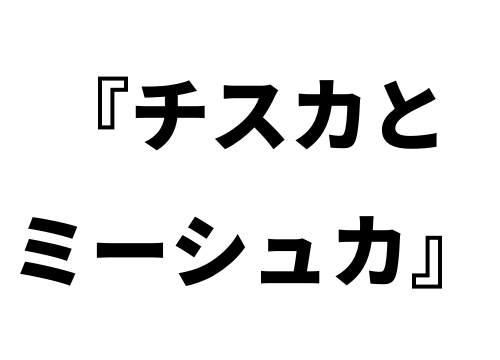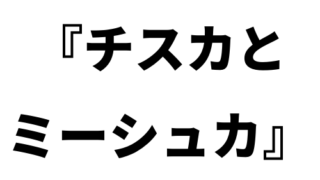「声だけで人を好きになることがあると思う?」
深夜のラジオから聞こえてきた言葉だった。あるさ、あるに決まっている。私はそう思った。彼女の声を聞いていると、こんな不幸の掃き溜めのような部屋でさえ、何にも代えがたい愛おしい空間に思えてくるのだから不思議だ。シンクには溢れるまで洗い物が溜まっている。温かい時期はコバエが湧く。ネットが買ったコバエ取りのカバーを開けて、何匹捕まっているか確認するのが夏の日課だった。布団用の消臭スプレーは最後に使ったのがいつかもわからない。噴出口に埃が詰まっている。カーテンの端は、レールから外れてみっともなくぶら下がっている。昔好きだった芸術家が本に書いていた。「生活のすべてが自分の表現である。」彼曰く、人間が頭の中で考えることはいたく重要だが、それは後には残らず、世界から見れば存在しないのと同じだそうだ。生活というのは、自分が何をしているのか、そのひとつひとつの行動のすべてと言い換えて良いという。生活こそが自分が世界に出力しているものであり、表に現れて、この世に残る自分である。つまり、それが自分の表現であるということだ。自分が寝ている姿、スマートフォンをいじって大して興味のない芸能ゴシップを延々とつまみ読みしている。レトルトカレーをレンジで温めて食べる。何回前のものかわからないルーの跳ねた汚れがレンジの内側の壁にひっついている。空になったパウチが、汚れた皿やスプーンと一緒にシンク投げ捨てられている。朝起きてもカーテンを開けない。何かの拍子に思い立って出したアイロン台は、出しっぱなしでもの置きになっている。火災保険の更新はがき、めったに使わないブルーレイレコーダーのリモコン、爪切り、プラグのUSB変換アダプタ、文庫本に挟まっていた栞、中途半端に残って飲まなくなった漢方薬。そういった行き場の定まっていないものを何でも置いた。窓のサッシには砂が溜まり、網戸に空いた穴はガムテープで塞がれている。これが私の表現らしい。私という人間は、このように世界に存在しているということだ。
何も面白くもない、刺激的でもなければ、展開すらない、そういう不幸にじわじわと絞め殺されていくのだと思う。最近私の感じた痛みで最も派手なものいえば、ベルトに乗った腹に生えた毛がバックルに巻き込まれた痛みくらいのものだ。妻が死んでからはずっとこうだ。妻は僕を憎んだまま死んでいったのだろう。死ぬときに僕のことでの後悔など何もなかったに違いない。いや、もしかすると僕と出会ったことを後悔したかもしれない。最も現実的なのは、僕のことなど思い出しもしなかったというパターンだろう。
水曜の深夜になると、この掃き溜めに彼女の声が響く。リスナーの悩みに答える合間に、古めの曲がかかる。シガーロス、フィッシュマンズ、ヌジャベス、ペイヴメント、ファンカデリック。歌詞が少ないか、英語なので何を言っているのかわからない曲が多い。彼女の選曲が好きだ。音楽に興味がなかった私は、彼女の選曲から多くの音楽に触れた。素晴らしいと思う曲とたくさん出会った。しかし、私が死んで三途の川まで歩いていくときに想う音は、これらの曲ではなく、きっと彼女の声だろう。そして彼女の声を聞いた思い出の場所は、この掃き溜めなのだ。そう思えば、なんと素晴らしい空間だろうか。
「難しいお便りだなあ。ちょっとしばらく考えてみるから、曲に行きましょう。」
仕事には行っている。漬物の工場で調理とパック詰めの工程管理をしているが、長期的なスケジュール管理や仕入れ元と卸先などを相手にした調整は総合社員の仕事だ。専門社員の私は日ごとの管理をするだけ。1年もしないうちに仕事には慣れた。毎日の始業から就業までで明確に途切れる仕事だから、前もって言えば休みも取りやすい。都会のオフィスで数字と向き合っていた仕事よりもずっと良い。収入はずいぶん減ったが、もう養う家族もいない。妻は娘の居場所さえ残さずに死んだ。娘が父親のことを知りたいと思えば、私までたどり着くのはそう難しいことではないはずだ。しかし、妻が死んでから10年以上が経つというのに会いに来る気配はない。つまりは、そういうことなのだろう。妻が娘に何を語ったかはわからない。会いにいくような男ではないと思われていたことは確かで、それを娘も信じているのかもしれない。私から妻の親戚筋を当たっても娘にたどり着くことはできるだろうが、妻が自分の家族に語ったであろう私の話を想像すると、何も良いことが起きないことはわかる。とにかく娘はもう立派な社会人のはずで、いずれにしても私のお金が要り用なことはないはずだ。ないことを祈りたい。祈りたいのは娘のためだ。私のためではない。今の職場は人の顔色を窺う必要があまりないのがいい。前の仕事では取引先と部下の顔色を常に窺っていた。下請けのときは取引先の顧客も出てきて彼らの顔色も窺った。何を考えているかわからない部下は急に辞める。それを私が上司に報告する。私は謝る。私は誰かが私の顔色を窺うあまり要らぬストレスを抱えていないか、自分の振る舞いを注視する。私は同じ年齢の平均的な会社員よりは仕事で成果を上げていたと思うし、よく稼いでもいた。しかし、どうでもいいことに心血を注いでいると気づいていた。どうでもよくないこととは何なのかもわからなかったし、それは今でもわからない。どうでもいいことに心血を捧げることからだけは逃げおおせた。
今は水曜の夜。
「明日もお仕事なのに遅くまで聞いてくれたみんな、ありがとう。ところで、」
水曜の夜だけが来れば良いと思う。動画サイトで常時配信されている東京の繁華街に設置された固定カメラの映像を見ることがある。ネオンの看板の間に消えていく男女は今まさに繋がっているのかもしれない。雨の日は路面に映る電灯がチラチラと動いて、海外の映画の冒頭シーンを思わせる。実際にその揺らめきを作っているのは、タクシーや大学生や居酒屋のキャッチなど私が心底興味のない社会の営みだ。倒れている飲んだくれを見つけた日はラッキーだ。私が勝手にそう決めている。運勢というのは誰かが勝手に決めているのが世の中でウケているだけなのから、私にウケるやり方で私が勝手に決めたラッキーでいい。我ながら自堕落で趣味の悪い生活だと感じる。私が本質的にそういう人間だからだろうか、そういう生活、つまり自堕落で趣味の悪い表現をしているほうが、妙に安心するのだ。しかしそれは不必要な安心だ。こんなものはすべて寝ている間に過ぎてしまって、何も知らないままでも一向に構わない。水曜の深夜、ラジオが終わったら眠り、起きたらまた水曜の夜。そのほうがずっと良い。いや、もしかすると起きたら水曜の朝というのも良いかもしれない。やっと今夜だ、と楽しみな気持ちで1日を過ごせるから。
「さっきの質問だけど、私は声だけで人を好きになるって素敵だと思うな。」
私には彼女の声の形がわかる。彼女の声の色が見える。彼女は、彼女の声で心に安らぎを得ている人間がいることを、ちゃんと知っているだろうか。その声がどうか永遠に若く、美しくありますように。そして、年を重ねて、優しく老いていきますように。彼女がある日のラジオで、「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」という映画が好きだと言っていた。すぐにDVDを注文した。余命僅かな若者が海を見るために病院を抜け出すといって、物語が始まった。僕が死を目前にしたら、いったい何を見に行きたいと思うのだろう。
「でも会いたくはないって気がするのが不思議だよね。」
声の主である彼女に会いにいきたいわけではないと思う。おそらく、人間が何かを愛するときは、愛の対象との距離を含めて一緒に愛するのだ。愛していればいるほど近くにいたいという単純なものではない。あの人とはこの距離、この人とはあの距離、その関係性を含めてやっと愛せる。ちょうどの距離感から誤って外れると、愛は壊れてしまう。この世界には、知らないままのほうが良いことのほうが多い。
「きっとわからないままでいたいってこともあるんだよ。」
わからないままでいたいという気持ちは、わかってほしくないことがあるという意味を含むと思う。誰にも知られたくない自分もいる。一方で、わからないことは怖ろしい。この掃き溜めは、妻は、娘は、この仕事の行く末は、私の未来は。それでも彼女の声を聞いているときの私は希望を感じる。なぜなら、
「わからないっていうのは、自由ってことだから。」