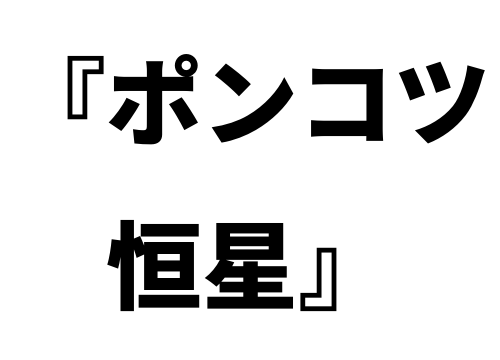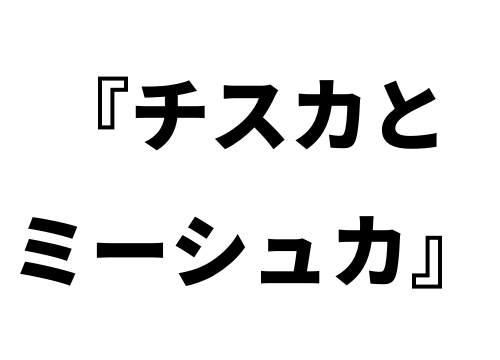Your Inside (短編小説)

Contents
1. 月と黒猫
真っ黒い猫がしっぽを揺らして夜を闊歩する。粉雪が舞う夜。月明かりが照らす暗い道を散歩する猫に、行く当てなどなかった。にゃあお。大きな声で鳴いたのに、周りには誰もいない。にゃあお。猫は黙ったまんまの夜空に向かって、もう一声鳴いた。
この街の夜は、からっぽ。からっぽ。 からっぽ。
にゃあお。にゃあお。にゃあお。
誰にも気づかれないとわかっていても、その黒猫は夜空に鳴き続けた。
ここにいるよ。僕はここにいるんだよ。
からっぽの街にその鳴き声はよく響いたが、誰にも聞こえてはいなかった。
夜空を見上げる黒猫の瞳は、月の光をたたえていた。真っ暗な道を見透かすことは、暗闇に慣れた猫にとってはなんてことのないことだったが、何を見つけるわけでもなかった。ただその小道には、黒猫の瞳に映った月の形が浮かび、彼の鳴き声だけが、がらんどうに響いていた。
にゃあお。にゃあお。にゃあお。
2. ギターと少女
午前2時。ベッドに入って枕を抱きしめる少女は、まだ起きていた。暗い考えばかりが頭を巡っていた。
「あんた、おかしいよ。」
つい半日前に言われた言葉。違う、おかしくなんかない。そう言い返せない自分が情けなかった。彼女にとって他人とは常に疑問の対象だった。
どうして人間は嘘をついてしまうんだろう。なにが人に嘘をつかせるのだろう。なんで人は、嘘の上で楽しく笑えるのだろう。そしてそれは間違ったことなのかなぁ。
どうして人は強がるんだろう。なにが人を強がらせるのだろう。人はいったい何をいるんだろう。受けいれてもらえない怖さが、かえって人を傷つけるのかなぁ。
彼女は髪の一部を赤く染めていたので変に目立つところがあったが、彼女の性格はそれほど活発で目立つほうではなかった。彼女には自分の世界があり、その中で理解した正しさが、外の世界でも同じく正しいものだと思っていた。しかしそれをわざわざ他人に押し付けるほどの図々しさを、彼女は持ち合わせていなかった。半日前までは。
頭がいっぱいで眠れない少女はベッドから起き上がると、窓辺に行って月を探した。しかし何も見当たらなかった。まだ雪が降っていて月は雲に隠れているのか、そもそもこの窓からは見えない位置にあるのかもしれない。誰かの泣き声がふと聞こえた気がしたが、濡れている頬に気が付き、それは自分の声だと理解した。
机の上に目をやると、そこにはたくさんのCDが無造作に積み上げられていた。これが誰にも理解されない、彼女の世界のすべてだった。真っ暗な部屋でイヤホンから響くギターノイズ、何度も繰り返し聴いたリフ、すべての美しさを教えてくれた歌声、すべてを形作ってくれた歌詞。彼女はそれを必死になって聴いてきた。自分自身を確かめるように。大切なものを手の中に握りしめるように。
気が付けば彼女はギターを手に取り歌っていた。ギターをかき鳴らす少女の表情は、もはや暗くはなかった。強い想いで弱者の歌を歌う彼女は、からっぽの街に生まれた最初の産声のようだった。歪む程の音量でギターを弾く午前2時。この生涯はその為にあるのか。
全然平気じゃないや あいつの目が嫌いだ
あいつらなんて 正常ぶって威張っているだけ
「うるさいよ!2時半だよ!」扉をあけて少女の母が怒鳴った。暗い部屋に引き戻された彼女はイヤホンを外して母親を見つめる。自分が鳴らしていたギターの余韻の大きさに驚いた。母は眠たそうな目をしていた。そうだ、さっき私のお弁当に入れるから揚げのした準備をしてくれていて、寝るのが遅くなったんだっけ。私の大好きな手作りのから揚げ。
「ごめん、お母さ・・・」
「こんな時間に!あんた、頭がおかしいんじゃないの!?」
少女の声を遮って怒鳴った母親は、扉を開けたまま寝室に戻っていった。
ごめん、お母さん。
少女の目からは涙が溢れていた。
あんた、おかしいよ。
昼間に友人に言われた言葉が再びこだまする。 そうだね、私、おかしいよ。
紺のセーターと赤いマフラーを身に着け、コートとギター持って彼女は家を飛び出した。
粉雪が降る街を、自転車にのった少女は泣きながら駆けた。こんなに泣いているのに、寒さを気にして着替える余裕があったことが、おかしかった。少女の涙は雪に混じって溶け、彼女のすすり泣く声と自転車の軋む音だけが、からっぽの街に、やけに大きく響いていた。
3. 傷痕と犬
その犬は左目に大きな傷があった。今では痛くもかゆくもないが、彼の顔の左半分は、いまだにただれているように痛々しく見える。昔、犬がまだ幼いころ、人間に蹴飛ばされて出来た傷だった。
想像の話。
その人間は死ぬ気だった。起きている間は常に、自分が生きていることで人に与え続ける迷惑について考えていた。自分の欲望や、社会での責任から逃げたいと思っていた。しかし彼の中にはまだ人のために生きたいという心が残っていたから、まずはこの息の詰まる苦しみの中で、呼吸をすることから始めようと考えた。しかし、そんなときに限って発作的に咳が始まり、それが望まれていない呼吸であることに気が付くのだった。
くそくらえ。すべてぶちこまえちまえばいい。死んだってかまわねえぞ。痛い。息ができない。痛い。いや違う、人間は変われる。旗は翻る。より良く生きるには・・・痛い。モルヒネをくれ。違う、輝かしい日々がいつかは・・・願望、失望、逃げたい。くそくらえ。痛い。痛い。いらだってんだ。おれは。死にたい。違う!呼吸をしたい。咳が止まらない。モルヒネを。くそ。痛い。逃げたくない。誰も傷つけたくない。痛い。息が。痛い。痛い。いらだってんだ俺は。前を通るな!
想像の話。
そして、
犬は蹴られた。
この人間は残酷だったわけでも、狂気の中にいたわけでもない。ただこういう状況に追い込まれただけだった。そして、蹴られた犬もまた。
傷はひどかった。菌が入り化膿が始まってからはさらにひどくなった。強烈な悪臭を放つようになり、顔は見るに堪えないものになった。臭いとなじられ、砂をかけられたり石を投げられたりすることもあった。ある公園のベンチの下に逃げこみ縮こまっていた犬は、当局に保護された。適切な治療を受けたおかげで左目の視力は問題なく残った。傷痕は消えなかったが、痛みは完全に消えた。治らなかったのは犬の心だった。人間に助けられたあとでも、蹴られた記憶とそのあとの苦しみが、人間に対する恐怖と不信感を深く刻み込んでいた。彼は心の中で小さくなって震えながら、近づいてくるすべての人間に牙をむいた。やがて彼にも心優しい引き取り手が現れたが、どれだけその家で過ごしても彼は人間を愛せなかった。引き取り手の女性はどこまでも優しく、彼の面倒を見続け、彼を愛したが、彼の心は荒れたままだった。そしてある日、ついに犬は人を傷つけた。
引き取り手の女性の隣に住む家族が遊びに来ていたとき、彼は久しぶりに多くの人間に囲まれたことに動転し、家族の4歳になったばかりの一人娘にかみついたのだ。さらにはそれを止めようとした引き取り手の女性をも、彼は突き飛ばした。この時までに1歳を迎え、成犬になっていた彼が飛び掛かれば、大人の女性くらいは軽く突き飛ばせた。しかし彼の心の中では、あの人間に蹴られたときと同じ幼い犬がしっぽを丸めて震えていた。家族が大事に育てていた沈丁花の鉢が彼の横で倒れていた。
犬の引き取り手の女性は彼を手放すしかなくなった。泣きながら彼を田舎道に置き去りにする彼女の手を、彼は初めてしきりに舐めたが、もう遅かった。女性は、ついに心を開くような素振りを見せた犬を撫で、左目の傷にやさしく触れてから、犬を置いて去っていった。
犬が左目の傷を舐めると、彼女の涙の味がした。犬は、誰にも聞こえない声で鳴いた。彼の横で揺れたのはムリカの花だった。
この犬は一番愛していたのは、実は引き取り手の女性の娘だった。学校から帰ってきたら姿を消していた犬を想って、彼女がどれほど泣いたか、この犬は知らない。
4. 雪と蝶々
雪はまばらだったので、地面は乾いていた。河原についた少女は、自転車を降りて、コンクリートの階段の一番上に腰かけた。空を見上げると、正面に月が見えた。さっき窓辺から探して、見つからなかった月。あなたがあの時に顔を出してくれていれば、お母さんを起こさなくて済んだのに。
粉雪がいまだ降り続く中、真っ黒に月の明かりだけを映す川を見下ろしながら、彼女はギターを取り出した。3月に降る雪は珍しい。冬の夢は、いつ覚めるのだろう。春の風は、いつ訪れるのだろう。
離れていかないで 蝶々みたく そっと近づいて 捕まえたりしないから
少しの間だけ 眺めさせていて 豊かな羽根が 開いて 閉じて
哀しむ間もなく 君は飛び立って行く 束の間の命は 伝えるには短すぎると思ったよ
風に吹かれて ふらふら 飛んでいる様は 私の人生のよう
束の間の観測は 心を動かすには 十分だったよ 命短し蝶々
待ってよ
分かり合えやしない 蝶々みたく 人の感情は 変わったり下がったり
でも少しの間だけ 眺めさせていて 私は考えて 笑って 泣いて
哀しむ間もなく 君は飛び立って行く 束の間の命は 伝えるには短すぎると思ったよ
風に揉まれて ふらふら 飛んでいる様は 人の情の波のよう
次は私の番だよ 分かり合えずとも 一緒に踊ろうよ 命短き私たちの 踊りを
分かり合えやしないの 分かり合えやしないの
でも でも でも …
ここなら彼女の歌を止める者はいなかった。いつしか東の空はうっすらと白み始めていた。
雪は止んだ。ギターを背負ってここまできた少女にとって、それは世界を背負っているのと同じだった。何度も何度も、春の風を想像して、同じ歌を歌った。今年の3月は寒い。明け方になっても、蝶々は現れなかった。
月は傾き、川の水面からその姿を消した。家に帰ろうと思い、立ち上がろうと手をついた先に一輪の花が咲いていた。ムリカの花だった。花言葉は”I can’t change anything.” 何も変えることはできない。
「自分はコンクリートから生えているくせに。」
と少女はムリカの花に言い残し、自転車を押して河原を去った。
5. 黒猫と人間
黒猫は痩せていた。甘えるのが下手くそだから。街には丸まると太った猫もたくさんいて、黒猫も彼らのようになりたいと思っていたが、ある日一匹の肥えた猫がこう言った。
「人間なんて簡単だよ。目を見ればわかる、そいつが猫好きかどうかね。猫好きだとわかれば、鳴きながら近づいて頭を足に擦り付けるんだ。手を出してきたら喉をゴロゴロ鳴らしながらひっくり返って腹を見せてやればいい。手で空を掻くのも忘れるな。そうすれば飯が貰える。太れば太るほど簡単になるぜ。」
これを聞いた黒猫は、生きるということは難しいと思うようになった。彼が鳴くときは本当に鳴きたいときだが、それは誰にも聞かれないので、黒猫は、彼がからっぽの街に鳴いているのか、彼が鳴くから街がからっぽなのか、もうわからないような気がしていた。
彼は人間が大好きだった。しかし甘え方がわからなかった。肥えた猫たちも人間が大好きだったが、それは食べ物が貰えるからだった。彼らが人間に甘えているのを見るたびに黒猫は、不平を言った。
「説明できる理由があるなら、そんなの好きって言えないよ。」
「じゃあ理由がないのに君は人間が好きなのかい。」と他の猫は返す。
「好きだから、好きなんだよ。」黒猫は自分でもおかしいと思った。
「そんなのって変だ。でも好きならもっと甘えればいいじゃないか。」
黒猫は黙っていた。
「なんで甘えないんだい?別になんだっていいけどさ、食べ物がもらえるから好きってのが悪いなんてこともないだろう。人間だって嬉しそうなんだから、いいじゃないか。」
黒猫は反論も納得も出来ずに黙っていた。ただ伝わらないことが悲しかった。黒猫と話していた猫は困った顔でため息をつくと、大きな体を揺らして仲間の元へ戻っていった。
黒猫は食べ物を探すことにした。人間からもらう食べ物がすべてというわけではなかった。街を歩いていればなんだかんだ食べるものは手に入るものだった。
からっぽだったのは胃袋ではなくこの街で、渇いていたのは喉ではなく黒猫の心だった。
彼の足は、街から離れた方向へと向かっていった。
6. 犬と大口
犬は捨てられた後、街で野良犬として生き始めた。人間におびえる犬は多かったので、彼は特別ではなかった。それでも街には人間が廃棄した食べ物がたくさんあったし、野良犬に食べ物を与えるお節介な人間も少なからずいたので、苦悩はあるが何年だって生きているくらいだった。彼は捨てられる前に少女に噛みついたことと引き取り手の女性を突き飛ばしたことを、ずっと後悔していた。しかし、それでも人間が近づいてくると牙を剥きだして今にも飛び掛からんとする勢いで威嚇することしか出来なかった。どれだけ威嚇しても、その臆病な犬には人が近づいてきた。こんなに大きく醜い傷跡がついた犬なのに、近づこうとする人間が多いことに彼はいらだっていた。他の野良犬よりも多くの人間に近づかれているような気さえした。そしてその近づいてくる人間も、やはり彼に怯えているのだ。時々、ある人間が、威嚇する犬とその傷跡に臆しながらも、食べ物を置いて行ってくれることもあった。彼はその人間が完全に見えなくなるまで威嚇を続け、その食べ物にもそう簡単には手を付けなった。しかし、その周りで臭いを嗅ぎまわりながらずいぶんと経った後、空腹に耐えかねて終にはそれを口にいれるのだった。
そうした様子を垣根越しに見ていた老婦人が犬に声をかけた。
「ずいぶんと苦しんでいるんじゃないかい。それじゃああんたを蹴飛ばした奴と同じだよ。」
犬は最初たじろいだが、老婦人が垣根の向こうにいることで多少落ち着きを取り戻した。
「なぜ犬の言葉がわかる。」
犬の言葉と聞いて老婦人は笑った。
「いやだね、そんなものわかりゃしないよ。でもこの年まで生きるとね、いろんなものを見たり聞いたりしてくるもんなんだよ。怒りも悲しみも知っている。それでも、なんでだろうね、すべてそれでよいと思えてくるんだ。そうすると心は穏やかに開く。実はみんなおんなじ言葉を持っているってことが、あんたにもそのうちわかるよ。」
犬は全然納得できずに言い返した。
「あなたはきっと本当の苦しみを知らないのだ。穏やかでいることなどもう俺にはできない。あなたは老いている。きっと俺に悪さはしない。それでももしあなたがこの垣根を越えて俺に近づいたら俺はきっと飛び掛かるぞ。恐怖があるからだ。怯える俺の心を守れるのは、この牙だけだ。」
犬は牙をみせて唸った。
「おやおや、小さいのにずいぶんな大きな口だね。」
老婦人は犬を横目に見ながら縁側へと戻っていった。
「人間に蹴られて裂けた口だぞ。」
「あんたの口の大きさのことじゃないよ。愛されたきゃあまずは、愛する勇気を持つことだね。過去の慰めを期待するのはそれからだよ。がんばりな。」
そういって老婦人は障子を閉め、家の中に戻った。
犬は街の外れまで歩いていくと、ひとりになるために、森の中へ入っていった。
7. エビと黒髪
川沿いに自転車を押していると、少女は凪いでいる川の浅瀬に赤いエビを見つけた。彼女は取ってやろうと思った。ギターを自転車にかけて川へと近づく。おかしなことをしていると、彼女は気が付いていた。しかし、おかしいとわかっておかしなことをしているのだから、それは自分が正常であるということだと思った。何より彼女は、先ほど彼女の前に咲いたムリカの花を見返したいということで頭がいっぱいだった。これを取って帰って窓辺に置いた金魚鉢に入れよう。面白いものを見せてあげるといって、お母さんの手を引こう・・・、なんて、高校生にもなってバカみたい。
それでも少女は川辺から手を伸ばして、水に触れた。しかし彼女が水に触れた途端、赤いエビは川の奥へと引き戻りはじめた。今の今までは「ここからは動きませんよ。」という顔をしていたのに。動くのなら捕まえられないと思い、諦めて戻ろうとした瞬間、少女は左足を滑らせて川に落ちた。彼女の左足はくるぶしの数センチ上まで水につかった。ムリカの花が頭の中で揺れていた。濡れてしまったのならもう一緒だと思い、彼女は両足で水に入り、後退する赤いエビを追った。しかしエビはそろそろと川の奥へ奥へとゆっくり逃げていく。まるで彼女を川の底へと導くように。少しずつ深く深く。あと少しで、あと少しで、というところで赤いエビは後ろに下がり彼女の手から逃れ続ける。気が付けば彼女は膝の下まで水につかっていた。3月の川の水は冷たかった。エビは、ふっと一瞬で、川の底へ姿を消した。
諦めて自転車に戻り、携帯で時間を見ると、もう午前6時になっていた。空はほとんど明るい。彼女の両親はいつも彼女が起きるより前に家を出る。足をこんなにぐしょぐしょに濡らした姿で早朝に帰ったら、なんと言われるだろう。きっと家族は、彼女は今部屋で寝ていると思っているはずだから、彼らが家を出てから帰ることに決めた。
自転車をゆっくり押しながら歩くうち、国道に出た。まだ点灯して走っている車も多い。濡れたふたつの靴はまだ行き先を知らないようだった。エビは後ろにしか跳ねられないと聞いたことがあった。実際にあの赤いエビはそうやって、彼女と目を合わせたまま後退してその手から逃げおおせた。後ろ向きの赤い生き物。
「私ってエビみたい。」少女は、自分の赤い髪と赤いマフラーを見てそう呟いた。
国道を走る車は、彼女と同じ方向に進むのにずっと速く通り過ぎていく。車は彼女を追い抜き、赤いバックライトは時折点滅しながら遠のいていくのだった。川の水に濡れた靴下は、一歩を遅れて教えてくれる。空はもうほとんど晴れていて、西の低い空には、ようやく鉛色の雲を抜け出した星が薄っすらと、それでもとても綺麗に輝いていた。しかし彼女は下を向いて歩き、濡れた足元から一歩ごとに染み出る水ばかり気にしている。彼女が背負ったギターは次々と追い抜いていく車のフロントライトに順々に当てられていた。彼女の世界は、点滅していた。
家に戻ったころには街は完全に朝を迎え、晴れ間ものぞき始めていた。彼女の足は冷え切っていたので、昨日の昼間の一言や、タイミングの悪い月や、ムリカの花や、赤いエビのせいで頭の中をぐるぐるしていたものはとりあえずどうでもよい気分だった。車がなかったので家にはもう誰もいないとわかり、玄関の鍵が開いていたので、両親は彼女が家に残っていると思っていたとわかった。安心して家に入り、まっすぐに温かいシャワーを浴びた。とても幸せな気分で、安堵していた。川から上がってから時間が経つにつれて彼女の足はどんどん冷え込んでいき、両親が家を離れるであろう時間まで待っている間は痛いくらいに冷えた両足のことしか考えていなかったのだ。過去や未来のことで悩むのは、現在に早急悩ましいことがないからだと、少女は思った。そして今少女は、先ほどまで頭をぐるぐる回っていたものから少し距離を置き、その瞬間の幸せ、つまり温かいシャワーの幸せに満足していた。そして、赤いエビはそれを彼女に教えるために現れたのだと思った。
髪を乾かし、温かくしてベッドに入ると、少女はたちまち眠りに落ちた。目が覚めたころには昼前だった。鏡の前に立つと、だいぶ色が落ち、どこか茶色のように見え始めた自分の髪を眺めた。エビの髪。肩にかかる毛束を手に取り、それを後退するエビのように自分に顔の前で動かしてみる。彼女は髪を黒く染めなおすことにした。またシャワーを浴びなければならないが、寝起きの表情はひどかったので、どちらにしてもシャワーを浴びるほうがよかった。髪を染めるのには慣れているので、大した手間ではない。
赤いエビは再び姿を消した。久しぶりの黒い髪に彼女は少し嬉しくなったので、服も寝間着から薄手のセーターと丈が長いスカートに着替えた。もう昼を過ぎつつあったので今日は学校に行かないことに決め、何か食べようとキッチンへ足を運ぶと、お弁当が置いてあった。蓋を開けてみると、少女がお気に入りの手作りのから揚げが入っていた。彼女はひとつを指でつまみとって口に放り込み、昨夜母を起こしてしまったことを考えながら、から揚げを味わった。弁当の蓋を閉じて、リュックに入れ、彼女はコートつかんで外に出た。学校にはもう行かないことにしたが、家でお弁当を食べるのは済まない気がしたからだ。しかも今日のお弁当にはから揚げが入っているのだから。
エビフライじゃなくてよかった、と少女は思った。でも、それはそれで笑えたのかな。
8. 犬と記憶
愛されたきゃあまずは、愛する勇気を持つことだね。過去の慰めを期待するのはそれからだよ。
森の中をさまよいながら犬は老婦人の言葉を反芻していた。彼を蹴飛ばした人間はたったひとりであった。その後に彼が出会った人間は何人いて、それぞれ彼に何を言い、何をしただろうか。
傷ついた彼を横目に無視した人々、傷のえぐさに目を背けた人々、ベンチの下で威嚇する彼を捕まえた人、ガラス張りのケージに彼を入れた人、傷の処置をした人、治るまでの間彼に餌をやった人、その後引き渡された保護センターの人々、他の犬を選んでいった里親たち、引き渡されるまで彼の面倒を見た人、彼を引き取った女性とその家族、彼が傷つけた娘とその家族、捨てられた彼に近づこうとした人々、食べ物を置いて行った人々、そして垣根の向こうの老婦人。
犬は歩きながら今までの記憶を振り返っていた。森という周りに誰もいない状況が、彼の考える時間と余裕を守っていた。そして彼は、自分が人間にしたこととしなかったことを考え、結論にたどり着いた。
人間が犬を蹴ったので、犬は人間を恐れ、人間を襲った。
犬があの娘に噛みついたので、きっと娘は犬を恐れるようになった。
あの人間が犬を蹴ったので、犬はすべての人間を恐れた。
犬があの娘に噛みついたので、きっと娘はすべての犬を恐れる。
犬があの娘に噛みついたのではなく、過去が犬にそうさせたのだ。
では、犬を蹴ったあの人間は何故犬を蹴ったのか。
―そうか、俺は、あの俺を蹴飛ばしこの傷痕を作った人間と、同じなんだ。
犬は自分が醜い憎しみの連鎖の中で生きていたことに気が付いた。また老婦人の言葉が脳裏に浮かぶ。本当に醜いのは、傷痕がある彼の顔ではない、別の何かであった。
森はいつの間にか薄暗くなっていた。ずいぶんと森の中を歩き回った犬は自分がどこにいるかわからなくなっていた。3月の夜はまだなんとなく寒かった。良く晴れた夜だったから、空にはたくさんの星が出ていた。少し街から離れるだけで、星はずっとよく見えるようになる。しかし犬はひとりになるために森に来た。そして星を見るために来たわけではなかった。彼は誰にも見られない場所に来たかったのに、たくさんの星が彼を見下ろしていた。1000の目が彼に迫ってくるようだった。
どこか光のない場所へ、星から見えない場所へと歩みを速めた犬は、森の奥に使い捨てられた車庫のようなものを見つけた。車庫の出口からは車一台なら悠々と通れそうなけもの道が曲がりくねって進んでいて、何年も前のものだろうが、草に隠れた太い二本の轍があるのが見て取れた。犬は錆びて赤色になったトタン屋根の下に潜り込むと、車庫の中に古い布団が投げ捨てられているのを見つけた。星の目からついに逃れた犬は自分でも気づかぬままに布団にくるまり目を閉じた。逃げておおせた野良犬は、頭の中で繰り返しこう呟いた。
俺は醜き動物にありました。人間を憎み人間を恐れたのは、人間を愛し人間に愛されたいと、本当は誰よりも強く思っていたからでした。それなのに俺の腹ときたら、人の飯を食ってだらしなく垂れているのです。この森を歩く、頼りなき足取り、頼りなき面持ち。醜き動物は自分を許すことなど到底出来そうもありません。自分に価値を見出せそうにありません。愛を求めるには早すぎたようです。そんな権利はなかったんだ。醜き動物には愛も価値もないのでした。
犬はいつの間にか眠りについた。車庫の外、夜の中に咲くムリカの花を、1000の星が照らしていた。
9. ブランコとピエロ
青空の下で過ぎていく時間をゆっくり眺めるというのも久しぶりだった。少女はブランコに乗って、ゆったりと揺れる。平日だというのに、午後早くブランコに乗っている少女は道行く人々にはどう映っただろう。風を浴びるその笑顔は、どこかわびしいと言っているようだったかもしれない。
公園の広場には、園児たちとその母親が何組かいて、その中心でピエロが風船を配っていた。彼女はブランコを止めて、膝の上でお弁当を開けた。今頃みんなはきっといつも通り教室で机を合わせてお昼を食べているんだろうなあ、と少女は思った。教室の風景を浮かべると、昨日のことが思い出される。
あんた、おかしいよ。
“違うこと“は罪なのだろうか。これは少女が常々抱いてきた疑問だったが、やはりそう言われると、発作的に心が縮こまるのを感じてしまう。昨日感じたその発作が蘇ってくるようで、緊張した彼女の持つ箸から唐揚げがひとつ落ちた。ピエロはまだ風船を配っている。笑ってさえいれば他人は自分に近づいてきてくれて、それで幸せなのかもしれない。その笑顔がたとえ仮面でも。人の話に合わせて同調していれば他人は自分を仲間だと認めてくれて、それで幸せなのかもしれない。たとえそれが本心と違っても。少なくとも公園のピエロは人気者だった。そして少女は、自分の周りの人間にも、今彼女がピエロに感じているのと同じ滑稽さを感じることがあった。
食べかけのお弁当に蓋を乗せてブランコの上にそっと置くと、少女はピエロの方へと歩いて行った。ピエロの周りにいるのは、若い母親たちに連れられた幼児たちと、下校中の低学年の小学生くらいだったので、少女は少しその間を抜けてピエロまでたどり着くのに躊躇した。しかしピエロを見習った笑顔をつくりながら会釈すると、母親たちは笑顔で会釈を返し、子どもを引き寄せて少女にピエロを譲ってくれた。
「あの、風船ほしんですけど・・・」掠れた声で少女が言うと、ピエロはただ笑って彼女を見ていた。実際は彼女の声が小さすぎてよく聞こえなかっただけなのだが、彼女は「高校生が風船を欲しがるなんておかしい」と思われたのだと感じ、急いで付け足した。
「ええと、妹にあげたいんです。」
ピエロはすぐに風船をくれた。少女は場の空気が柔いだような気がしたが、それも気のせいかもしれない。
「すいません!」
少女はピエロに素早く浅いお辞儀をして、その場を離れた。ピエロが手を振ってくれたのと、ひとりの母親が微笑ましいという表情を少女に向けていたのが彼女の目に入った。
ブランコに戻ってきた少女は、ブランコの鎖に風船を括りつけ、再び腰かけた。彼女は笑いたいような気分でもなかったし、妹もいなかった。ただ、風船貰いに行くときに期待される表情やセリフを考えてやってみたのだった。彼女はそれなりにうまくやれたのだろうと思ったが、嫌な疲れと違和感が残った。特に最後に母親が少女に向けた「優しいお姉さんね」という表情を思い出すと、罪悪感が込み上げてきた。
ただの嘘つき。良い人。
そのとき少女驚いて足をあげた。突然何やら柔らかい毛のようなものが彼女のふくらはぎに触れたからだ。ブランコの椅子の下を覗き込むように見ると、一匹の黒猫がいた。ああ、なんてかわいいんだろう。違和感や罪悪感にまみれかけた少女の気持ちは、突然の来客に一瞬ほころんだ。黒猫は少女の目をじっと、後ろ手に何かを隠しているような目で見つめた。瞳の奥にはうっすらとした緊張があった。
「大丈夫だよ。」
少女が手を伸ばして黒猫に触れようとすると、黒猫はいかにも猫らしい素早い動きで、さっき少女が落とした唐揚げに手をかけて、咥えた途端走り去った。
10. 黒猫と犬
黒猫は唐揚げをくわえたまま森に入った。舌に感じるこの上ない味の誘惑に負けそうになりながらも、なんとか森の奥まで進み、赤いトタン屋根が見えてきた。黒猫は唐揚げを置いて、車庫に向かって話しかけた。
「ねえ、食べ物を持ってきたから食べなよ。」
返事はない。黒猫はため息交じりにもう一度唐揚げをくわえて、車庫に入っていった。犬は毛布の上に丸まったまま、傷がついていない右目で黒猫をみた。犬は腹に骨の形が浮き出るほどに痩せていた。
「本当にいい加減なにか食べないと死んじゃうよ」
犬は迷惑そうにあくびをして、さらに顔を毛布に沈めた。
「どうして俺にかまうんだ」
黒猫は唐揚げを犬の近くに放ってから答えた。
「だって僕たちは似た者同士じゃないか。僕は君みたいに辛い過去があるわけじゃないし、一緒にされたら君は嫌かもしれないけど。」
犬と黒猫は数日前にこの森で出会い、黒猫は犬の傷についての話をすでに聞いていた。食べ物のために人間にすり寄ってばかりの仲間の猫から離れた黒猫は、森に入っていったのだった。
「お前と俺のどこが似てるんだ。俺は人間が嫌いだ。お前は人間が好きなんじゃなかったのか?」
「僕は人間が好きだよ。でも君も僕も、人間に近づくのをためらってしまうのは同じだし、君だって人間が本当は好きなんでしょう?好きだから、嫌いなんだよ。」
「よくわからないな」
「わかってるくせに。僕だって人間が好きだから、他の猫みたいに簡単に甘えられないんだから。」
犬は何も答えなかった。
「そういえば前から思ってたけど、君の首輪、僕は素敵だと思うよ。どこでもらったの?」
犬はまだ何も答えなかった。
「とにかくこれ、食べてね。僕だってお腹がすいてるんだ。このままここにあったら僕が食べちゃいそうだよ。もう行くからね。」
「じゃあ自分で食べればいいじゃないか。俺はいらない。」
「そういっていつも食べてるでしょ。」
黒猫は森から駆け出して行った。残された犬は立ち上がり、唐揚げに鼻を近づけた。
「この唐揚げ・・・」
犬は胸の奥底からなつかしさが湧き上がるのを感じ、唐揚げをほおばった。犬は再び毛布に丸まった。そして涙が溢れる眼を閉じて、瞼のうらの思い出の世界に沈んでいった。
11. 昼間と少女
お弁当を食べ終わった少女は、まだブランコに座ってピエロを眺めていた。じきに先ほどまで周りにいた園児と親たちは帰っていった。役目を終えたピエロも公園の隅に置いた大きなショルダーバッグを肩にかけて去っていった。ピエロには似つかわしくない、いやに事務的なショルダーバッグだった。妹がいないのに、妹がいると嘘をついた自分を思い出した。少女の上には、いまだに舞い上がることを諦めない風船がゆらゆらと揺れていた。
少女は昨日の昼に起きたことを反芻していた。
どうしてみんなはあんなことで笑うのだろう。何も面白くなんてないのに。平気なふりなんてしちゃってさ。自分たちは正常です、という顔をしてるんだ。
少女には同じクラスに幼馴染の友達がいる。友達は失読症を抱えていた。なんとか普通にやっていける程度の軽度の障害だったためか、彼女はそれをずっと隠していた。中学2年になったある日、彼女は自分が失読症であることを少女に明かした。誰にも言わないでほしいと言われたので、少女は約束を守ったが、その以来少女は彼女が陰で抱えていた苦労を知ることになった。彼女が最も苦労していたのは国語の音読の時間。いつも国語で新しい文章を勉強するときには、それがきちんと読めるようにお姉さんに助けてもらいながら一緒に必死で練習していたのだった。少女は友達を助けるために、始めたばかりだったギターのメロディーに乗せて、彼女のお姉さんと一緒に国語の文章を歌ったこともあった。
友達は高校に入ると雰囲気が変わり、部活動の仲間と一緒にいることが多くなった。少女と彼女は昔よりも一緒にいることが少なくなった。彼女は聡明な人間だったが、高校に入ってからは、快活で無知な少女を演じているように見えた。高校にもなると、現代文の時間に音読をさせられることはほとんどないが、時々あてられてときには居眠りしていたり教科書を忘れたといったりして誤魔化して、彼女は文字を読むことを避けていた。新しい仲間に茶化され、友達は笑っていたが、心の中ではみんなの前で音読するのが怖れているのが、幼馴染の少女にはわかった。そして昨日の4限目の現代文で先生にあてられたとき、いよいよ友達は音読をするしかなくなった。言葉がスムーズに出てこない。窓の外では、太陽が高く昇って、教室の半分を照らし出していた。
「…えっと、すみません何ページでしたっけ、あはは」
隣の席の男子が小声で教えてくれる。「136ページだよ、今開いてただろう」
「あ、そっか。えぇと、『よ、要するに、私の、、、こしん?の発うーん、、でした』」
彼女はなんとか読み取れる音だけをつないで、ぼそぼそした音でごまかしながら小さな声で読んだ。
「もう少し、大きい声で読めますか?」不思議そうに眉を細めた先生が言った。
「あ、はい、すみません」少し上ずった声で友達は言った。
クラスの仲間が彼女を茶化す。
「ちょっとー、どうしたの、ぼーっとしすぎでしょ!」
「ちゃんと読みなー、頑張れーあはは」
友達はみんなに好かれていた。からかいやすい可愛げが、クラスのみんなに受けていた。
「うるさいなー、もう!」彼女は笑いながらやり返して、再び教科書に目を落とす。彼女の眼は揺れていた。どう読むかではなく、どう読まないで済ませるかを考えるのに全身全霊をかけていた。
「うーんと、『せん、、、あれ、せい?精神…』、先生、ごめんなさい、先に呼んでもらっていいですか?そのあとで繰り返すので…」
先生は笑った。「どうしたの?読み方忘れちゃった?」
クラスもどっと笑った。
「えー、おバカすぎー、もう本当にかわいい~」
「どうやってこの高校受かったんだよお前」
友達は頭を掻きながら苦笑いしていた。早く席に座りたそうに、膝が揺れていた。
「いや~。今日はちょっと調子が悪いかな~?えへへ。先生、ここはひとつお願いします!」
それでも表情と言葉は、クラスのお調子者のそれを保っていた。
「わかりました。今回は私が読みますので座っていいですよ。ちゃんと授業を聞いててね。」
先生はあきれながらもほほえましそうに言った。
「では続きです。『要するに私の言葉は単なる利己心の発現でした。《精神的に向上心のないものは、馬鹿だ。》私は二度同じ言葉を繰り返しました。そうしてその言葉がKの上にどう影響するかを見詰めていました。』この“先生”の発言ですが…」
先生が音読を止めるよりも前にクラスは再び笑いに包まれた。
「『精神的に向上心のないものは、馬鹿だ。』だってよ、まさにあんたに言ってるんじゃない?あはは」
「ちゃんと授業くらい聞いてなよ~、ていうかこれが読めないのは本当にヤバいって!」
偶然音読された部分のセリフが、簡単な漢字も読めなかったと思われている友達の状況に重なったのが滑稽だった。
「バカじゃないしぃ~!たまたま読めなかっただけだもん!今日はちょっと漢字は無理な日かなって感じ?先生、ありがとね!」友達は明るかった。このクラスにそんな彼女のことが好きでない者はいなかった。教室が和やかな雰囲気に包まれた昼下がりを破ったのは、少女の一言だった。
「みんな、笑うのやめなよ。ふざけてやってるんじゃないんだからさ。」
中学の頃から、人知れず失読症と戦うために努力を重ねる友達の姿を見てきた少女にとって『精神的に向上心のないものは、馬鹿だ』というセリフが彼女に向けられているのは、納得できなかった。
少女の言葉に教室の空気は冷たくなった。生徒間のくだけた雰囲気に流されて微笑んでいた先生も、少女の言葉に態度を改めたようだった。
「う、うん」先生は少しせき込んでから続けた。
「そうですね、誰にでも間違いはありますから、授業中ですし、笑うのはやめましょうか。では、“先生”は何故このセリフをKに二度も言ったのでしょうか?考えてみてください。」
クラスの面々はただの楽しい茶化しあいをいじわるのように言われていくらか不服そうだった。
「別にふざけてるとは思ってないけどさぁ、本人だって笑ってるし。そういうキャラじゃん、ねえ?」
「そ、そうだよ、全然いいよ、あはは」友達はまた笑った。そして少女の名前を呼んで続けた。
「どうしたの?」
少女が黙って友達を見つめていると、彼女は言った。
「なに、怒ってるの?よくわかんない。あんた、おかしいよ。」友達は笑っていた。
気が付けば、ずいぶん長い間、少女はブランコの上に座っていた。ここから見える線路を、ピエロが帰ってからもう何本の電車が通ったことだろう。ピエロはもとの姿になって帰っていったのだ。今日学校にいるクラスメイト達も、そろそろもとの姿になって下校するのだろうか。
にゃあお。
近くで猫の鳴く声がした。ブランコの下を覗き込むと、さっきの黒猫だった。黒猫は少女のリュックの中に顔を突っ込んでいた。
12. 犬とさすらい
さすらいの男は街にいた。浅黒くなった肌はどこか異国の情緒を思わせた。古くなったハットをかぶり、砂漠をいく隊商が持っているような袋状のバッグを持ち、背中には小ぶりなギターを裸のまま背負っていた。八百屋の店主は男の変わった風貌に、はて、と思いながらも、その深く刻まれた笑い皺がたたえる寛容の色と、帽子の陰で存在感を放つ理知的な瞳に好感を持った。男はオレンジをいくつか買っていった。
さすらいは森に入ると、赤いトタン屋根の古い車庫を見つけた。火を起こすためにちょっとした穴を掘りたいと思っていた彼は、車庫から使える道具を借りられないかと考えた。車庫には何も置かれていなかったが、古びた工具がところどころに転がっていた。彼はかつて棚か何かを支えていたと思われる細いL字の金属の棒を拾いあげた。そして車庫からでようと思ったところで、古い毛布の上に、痩せ細った犬が丸まっているのを見つけた。
さすらいは金属棒を使って穴をこしらえ、その中で火を起こし、湯を沸かした。缶に入った乾燥茶葉を取り出し、湯で淹れた。
彼はオレンジの皮をむきながら、顔も上げずに言った。
「やあ、こっちに来て一緒に食べないか?」
犬は顔をあげてさすらいをみた。
「煙くてすまないね、こっちにおいで。君だよ、お犬さん。」さすらいも犬の方を見た。
「なんか喋ったらどうだい」
犬は驚いた。「あんたも俺たちの言葉がわかるのか?」
さすらいも驚いた。「あんたも、だって?君はこれまでにも君たちの言葉がわかる人間とあったことがあるんだね?それは珍しいな。ほら、オレンジ食うか?」
さすらいは土をかけて火を消し、犬の方へ皮をむいたオレンジを差し出した。犬は立ち上がったが、さすらいに近づくのをためらった。
さすらいは手元にあった金属棒を持って立ち上がった。犬は足をすぼめて後ずさったが、さすらいはそれを車庫の中のもとあった場所に返して戻っていった。
「そうか、オレンジよりもこっちのほうがいいのかな」
さすらいはバッグから干した肉を取り出した。
犬は腹が減っていたのでそれを食べたかったが、さすらいに近づくことは恐れたので、彼が肉をこちらに放り投げてくれることを期待した。今まで街のお節介な人間たちがそうしたように。しかし、さすらいにそうする素振りはなく、ずっと干し肉を犬の方へ差し出して待っていた。さすらいの瞳は、じっと犬の瞳を覗き込んでいた。
さすらいの目から友好の色を見て取った犬は、少しずつ時間をかけて男に近づき、ついに彼の手から直接干し肉を受け取った。硬くなった肉を奥歯で噛みしめる犬に向かってさすらいが尋ねた。
「その目はどうしたんだ?」
犬は答えた。「むかし、人間に蹴飛ばされたんだ。」
さすらいは少し息を吐いた。
「ああ、聞き方が悪かったね。傷のことじゃなくて、君のさ、目つきのことを聞いたんだ。でも、それも人間に蹴飛ばされたからなのかな。ひどい奴もいるもんだね。」
犬には返せる言葉が思いつかなかった。
「君の目は、愛を隠した色をしてる。」
さすらいの言葉に犬は目を見張った。いつかの老婦人の言葉が思い返された。
さすらいはオレンジを食べ終え、指に着いた果汁を舐めると、横においてあったギターを手に取った。
「おれたちの世界はさ、ちょっと生きづらいよな。だけどさ、なんだか苦しむのも苦しめるのも、結局は自分が悪いって気もしてくる。
とりあえずもっと食べな、君は痩せすぎだよ。」
さらに数切れの干し肉を犬の前において、さすらいはゆっくりと歌い始めた。
穢れきって腐りきった世の中 それを作り出したのは誰なのか
気づいてしまっている 大方 他でもない いない おれらしか
そうおれらだってそう 穢れきって腐りきっている
その精神に自己否定感を抱き 苦しんでいる 悲しき震源 発見
いくらおれがあんたの身体を 掻きむしってみたところで
愛なんて出てきやしないんだ そんなところには何もない
何を問いかけたって返答ねぇ 皆目見当付かないように見え
他人を突き飛ばして震えている あんたの心の中に食い込んでいきたい
本当のあんたを教えてくれ 小さくて弱いあんたを教えてくれ
あんたも知らないあんたを見せてくれ あんたの心の中に食い込んでいきたい
おれもあんたも同じだと思うよ だからこそ感じ取れたその表情は
怖がりで暗がりで怯えてたんだ あんたの 心の中に 食い込んで生きたい
13. 黒猫と少女
“「セリヌンティウス。」メロスは眼に涙を浮べて言った。「私を殴れ。ちから一ぱいに頬を殴れ。私は、途中で一度、悪い夢を見た。君が若し私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえ無いのだ。殴れ。」
セリヌンティウスは、すべてを察した様子で首肯き、刑場一ぱいに鳴り響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、
「メロス、私を殴れ。同じくらい音高く私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生れて、はじめて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。」
メロスは腕に唸りをつけてセリヌンティウスの頬を殴った。
「ありがとう、友よ。」二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。“
「ね、まだ覚えてるんだ。一緒に歌いながら覚えたんだもん。ギターだってそうやってうまくなったんだ。なんかさ、理想の友情って感じだよね、走れメロスって。」
少女は足元を嗅ぎまわる黒猫に向かって話しかけていた。黒猫はというものの、この少女に甘えたいと心から願っているのだが、どうやればいいのかうまくわかっていなかった。長いスカートの裾から見える少女のくるぶしに頭をこすりつけてみようと思うのだが、軽く頭突きを繰り返しているようなありさまだった。
黒猫は少女のリュックに頭を突っ込んでいたところを見つかり、再び逃げようとしたのだが、少女がリュックからお弁当を取り出したので踏みとどまったのだった。少女は黒猫がまた戻ってきたらちゃんとあげようと思って唐揚げをまだとっておいたのだ。その匂いにまんまとおびき寄せられた黒猫は、リュックに頭を突っ込むはめになったのだ。食べ物がもらえてから甘えるなんてズルいな、と黒猫は思ったが、気が付けば少女に捕まり、柔らかい膝の上で撫でられていた。
すでに日が傾き、東の空にはうっすら星が見え始めた。
「私、そろそろ行くね」
少女は黒猫を地面に戻し、手を振った。「バイバイ」
彼女が去ってから黒猫は少女が膝の上で聞かせてくれた話について考えてみた。そして、自分が人間の言葉がなんとなく理解できていたことに気が付いて驚いた。少女は昨日の昼に起きた出来事について黒猫に話したのだった。
黒猫は、にゃあおと鳴いてみた。公園にはもう誰もいなかったが、いつかの夜に感じたからっぽはどこかに行ってしまったようだった。黒猫の目には白い月が映り、黒猫の心には森にいる犬と、家路を行く少女の顔が浮かんでいた。
14. まどろみ
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
「『あんたの心の中に』って曲だよ」とさすらいは言った。
「俺にも傷があってね。でもそれを隠すために鍵をかけてさ、入ってこようとするものをみん敵だと思ってると、腐っちまうんだ。川っていつも綺麗だろう?流れているからだよ。だから俺たちも心を開いて、循環させないとダメなんだ。」
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
その後もさすらいは犬に向けてたくさんの曲を歌った。
「受け売りだけどね。この歌を俺に歌ってくれた人がさ、同じことを俺に教えてくれたんだ。」
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
「どうにかして、誰かの心の中に入っていくことができないかなとよく考える。その人を傷つけることなくね。どうしてか、傷つける言葉だけは、簡単に誰かの心の奥底まで届いちゃうんだ。気が付きもしないうちに。」
まどろみの中で…正体をみようとして、真っ暗を覗き込んでいる。まどろみが溶けだす。
「もしかしたら、誰かの心に入っていこうだなんて考えが間違っているのかもしれないけど、少なくとも俺の心は誰かを待っているような気がするんだ。だから他の心だってきっと・・・。言葉なんかじゃ足りないんだけど。言葉くらいしかと頼れるものもないんだけど。」
まどろみの中で、震えているのはまだ小さかった頃の犬。素直に求めることができたあるがままの心。犬が経験した物語が、その小さな心を囲んで閉じ込めている。まどろみをかき分けて、犬はそれに一歩一歩近づく。まどろみの中で、物語をかき分けて。
さすらいはなおも歌っていた。
「でもね、閉じこもったままの心と同じくらいに、その扉の前で待ち続ける心も、頑張ってるんだよな。次の曲の名前はね、『Your Inside』。」
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
少女にはまだ自分の世界を捨てる勇気はなかったし、そんな勇気なんてなくていいとも思っていた。しかし、疑いという気持ちが湧き上がるのをどうにもできなかった。
「あんた、おかしいよ。」
友達はそう言った。
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
少女にとって教室はまどろみであった。よく見えない、正体不明の空気が支配する嘘みたいな空間。
私、おかしいのかな。
友達はきっと失読症について他のみんなには知られたくないんだ。
私、余計なことを言ったかな。でも、あの子はバカなんかじゃないのに。
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
少女は失読症を隠したままでいなければならないような友情は悲しいと考えていたが、隠したままでいたいという友達の気持ちを出来るだけ尊重した言葉を選んだつもりでもあった。
言葉はいつも足りないし、人は変わっていってしまうものなのかも知れない。
まどろみの中に沈んでいった少女だが、窓に何かが当たる音がして、少女のまどろみは途切れた。
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
黒猫は公園の横の家の塀の上に座っていた。犬の物語と少女の物語は、黒猫にとっても悲しいものだった。しかし一方で、黒猫は自分には何もないということに気が付いた。犬には森に閉じこもってしまう理由があった。少女には自分の世界があり、それを友達に訴える勇気があった。黒猫には何もなかった。
まどろみの中で強い不安があった。正体がまるで見えなくて、目を閉じて、まどろんだ。
黒猫はからっぽだったが、今では犬や少女の物語が黒猫のなかにある。まどろみをかき分けても正体がないなら、それは自分で作ってこなかったからなのかもしれない。
黒猫は人間に甘えたい気持ちをずっと抱いていたが、何かと理由をつけて素直に甘えることを避けていた。
犬のために食べ物を持っていかなければという気持ちが、黒猫に繋がりを与えた。
黒猫は昼のことを思い出して、唐揚げをくすねたブランコの方を見やった。少女は食べ物をくすねた僕のために、唐揚げをとっておいて待っていてくれた。
ぼーっとブランコをほうをみてまどろんでいると、少女がブランコに括りつけた風船が、忘れられたまま揺れていた。
まどろみの中で強い不安があった。正体をつくるためにまずは、この風船を届けようと思い、黒猫はまどろみから抜け出した。ブランコの風船の紐を食いちぎって、少女の家に向かった。唐揚げの匂いがする方へ。
窓の外で音がして、少女はまどろみから覚めた。トントンと窓を叩く音がした。少女がカーテンを開くと、昼間の黒猫がいた。驚いた少女は窓を開けて、黒猫を招き入れた。
「どうしたの?猫ちゃん」
「風船を忘れていたから」と黒猫は答えた。
少女は思わず笑った。「嘘ついてもらった風船なんだ。ありがと。」
黒猫から風船を受け取った少女はそれをリュックに括りつけた。
「最初からこっちに結んでおけばよかったね。」と少女は言った。それを黒猫がジッと見ていたのに気づいて少女は付け足した。「あ、もう唐揚げはないからね。」
「そういうつもりじゃ…あの、さっきはありがとう。僕は君の唐揚げを盗んだのに…」
黒猫が、少し罰が悪そうにいうと少女は笑った。
「あはは、猫が謝ってる。偉いぞ。でも猫に盗まれて怒る人間なんている?君は可愛いなあ。」
少女は猫を持ち上げて、胸に抱いた。黒猫は目いっぱい少女の顔に自分の顔をこすりつけた。少女はますます笑った。
「猫に本気で怒る人間と思うよ。」と黒猫は言った。
「僕の友達に左目に傷痕がある犬がいるんだ。人間に蹴られたんだって。」
「ひどい人もいるんだね。」
少女はそう言いながら、確かにそういう人間や、そういう人間に苦しめられた動物にも覚えがあるなあと思った。左目に傷がある犬か…。
「ねえ、実は昼の唐揚げ、彼のところに持って行ったんだよ。ほっておくと全然食べないから。」
「その犬のところに?」
「うん。」
「そうだったんだね。ねえそのワンちゃんってまだお腹すかせてるかな。」
15. 蝶々と沈丁花
さすらいは歌う。
君を見つけたよ どんな想いも 元をたどったら いつもそこにいた
等身大の君を見る事は とてもムズカシイ事で
優しくて大きく感じた 君の手はホント小さくて
いけない自分 許せない自分 君のその腕の中に包み込まれたい
君も知らない僕の想いを 夜空に打ち上げたい throw it high 届け
本当だったらね どんな困難も 僕の手を握ったら 大丈夫だよって言いたい
等身大の僕を見る事は とてもムズカシイ事で
優しくて大きく感じた 僕の手はホント小さくて
苦しい気分 やるせない気分 僕のこの腕の中に包み込みたい
君も知らない 僕の想いは 流星となり君の胸に throw inside 届け
ねぇ 聞いて欲しいんだ できない事だらけの僕でも
この想いは確かなんだ 冷たく凍えた君の手 握りたいよ
伝えたい your inside
君を見つけたよ どんな想いも 元をたどったら いつもそこにいた
楽しい気分 そうでない気分も 僕らのこの腕の中に包み込みたい
君も知らない 僕も知らない 2人だけの星空を作っていきたい 届け
犬はまどろみから覚め、さすらいの声に耳を傾けていた。さすらいが歌い終わると犬は呟いた。
「ユア・インサイド…」
さすらいは答えた。「そう、『Your Inside』、あなたの内側。『あんたの心の中に』と何が違うんだと聞かれたら、難しいけどね。」
さすらいの前を横切って、白い蝶々が飛んできた。薄暗くなってきた3月の森の中に舞う白い蝶々は、幻想的だった。犬は立ち上がって蝶々を行く方を少し追ってみた。昨晩車庫の前に咲いていたムリカの花はいつの間にかなくなっていた。代わりにそこには一輪の沈丁花が咲いていた。
犬は蝶々を見失った。犬の足はさすらいの方へ向かい、前足をさすらいの膝に重ねた。
「よしよし。君は野良犬だね。でもこの首輪はどうした?」さすらいは両手で犬の顔を包みながら尋ねた。
「これは、前の飼い主が俺にくれたものなんだ。」
「そうか、いい家族だった?」
「人生で唯一、俺を愛してくれた人たちだったよ。」
「なんで別れたんだ?」
「俺が悪いのさ。俺が臆病だったから。」
「その傷と関係があるのか?」
「・・・そうだな、この傷が俺を醜くしたのかもしれない。」
「捨てられたのか?」
「・・・仕方がなかったんだ。俺が悪いんだ。」
「君、俺と一緒に来ないかい?これからちょっとした冒険に出ようというところだったんだが、相棒がいたらいいと思ってたんだよ。」
犬はさすらいと一緒に森を出るという未来を想像した。しかし、そうする前にさすらいには自分の過去について知ってもらおうと思った。犬は、黒猫に話したように、自分の過去について話し始めた。しかし、すぐにさすらいはそれを止めた。
「いいよ。そんなの話すなよ。これからいくらでも一緒にいるだからさ。俺には未来の話をしてくれないか?これから俺たちどうしよう?」
犬は未来のことなど考えたことがなかったので、面食らって何も思いつかなかった。
「俺と来るなら過去のことは置いていってもらう。その首輪もね。」
犬は困った。
「待ってくれ。確かにあんたはいい人だろう。あんたと行きたいよ。未来のことが考えられるようになりたい。でも…」
「過去に縛られることと、過去を大切に胸に抱くことは、全然別のことだよ。」
犬の前にしゃがみこんださすらいは、犬の顔に左手をあてて言った。
「一回全部降ろしていいんだよ。その中からもう一度、1つ1つ拾えばいい。本当に大切なものは消えやしない。だから大切になったんだ、そうだろ?そうしたらまたさ、そのときに君の大切な過去について聞かせてくれよ。」
16. 首輪と風船
少女はまた自転車をこいでいた。前のかごには黒猫が乗っていた。掴んできたリュックには急いで手近にあった食べ物を入れてきた。黒猫は少女に言った。
「ねえ、その犬だけど、実は人間を怖がってるんだ。前にひどいことをされたみたいで。」
「左目の傷の話?」自転車の立ち漕ぎに行きを切らしながら少女は返した。
「うん。だから僕が君を連れていったら困るかも…。」
「大丈夫だよ。」
少女は力強く言った。まるで確認する理由でもあるかのように。
「大丈夫。」
黒猫は少女を見上げたままだった。
「ねえ」
「だから大丈夫だって」
「いやそうじゃなくてさ、風船、ついてきてるよ。」
少女は自分のリュックから先ほど括りつけた風船が頭上に伸びているのに気が付いた。
「あはは、本当だ。」
「僕が持ってきてあげたやつだもんね。」黒猫は得意そうに言った。
やがてふたりは森に着いた。家を出るときは夢中だったので考えなかったが、少女は自転車のうえで、夜の森とはどんなものだろうと少し怖い気分になっていた。しかし、冬が終わったばかりだからか、思いのほか森の密度は低く、ひときわ明るく大きな月が森の地面にま明かりを届けていたので、少女はほっとした。
森の車庫に着くと、黒猫は犬を探したが、彼の姿はどこにも見当たらなかった。
車庫の前に掘られた穴から、微かに何かが燃えたあとの匂いがした。
「いなくなっちゃった。どこにもいないよ!」
黒猫は不安そうな顔をして、少女の足元に寄ってきた。
「ねえ、これは?」
少女は手に持ったものを黒猫にみせて尋ねた。犬が大切にしていた首輪だった。
「それ、彼が大切にしてた首輪だよ!前の飼い主がくれたんだって。なにかあったのかなぁ。」
黒猫は首輪をみて、さらに不安に思った。
大切な首輪を置いていくなんて。ちょっとどこかに出かけたというわけじゃないんだ…!
一方で、少女は首輪をみて微笑んでいた。大切そうに首輪を胸に抱いて、黒猫に言った。
「きっと、大丈夫だと思う。見て、この首輪、ここに置いてあったんだ。」
少女が指さした切り株の上を猫がのぞくと、摘まれた沈丁花の束とギターのピックがそこに置かれていた。
「沈丁花の花言葉、知ってる?」
「花言葉?」
「うん、前に家で育てていたことがあってね、ちょうど今が見ごろなんだよ。花言葉は、『不滅』。」
花言葉のことは黒猫にはよくわからなかった。しかし、少女がなぜか確信に近い安心感を持って首輪を抱いていることはわかった。
「ほらここ、何かを燃やしたみたい。ギターのピックもあるし、誰かここに来たんだね。」
しばらくの沈黙を挟んで、黒猫は少女に尋ねた。
「せっかく食べ物を持ってきたのにね。でも、どうして来てくれたの?実は僕もふたりが会えればいいと思ったんだけど。彼も君の唐揚げを食べたみたいだし。」
「んー、なんでかな。ちょっと事情があるから、うちで飼ってあげられるわけじゃないんだけどね。でもさ、まだ近くにいるかも知れないよ。ちょっと良いこと考えたんだ。」
そう言って彼女はリュックからマーカーぺンを取り出し、風船を紐から外した。
「この白い風船に色をつけて飛ばしちゃおう。何色がいいかな?」
黒猫は怒った。「ええー!せっかく僕が届けたのに。」
「君、願掛けって知らないのかい?君が届けてくれたからこそだよ。次は私たちの気持ちを込めて、そのワンちゃんに届けるの。」
黒猫はそういうものかと思い機嫌を直した。
「じゃあ僕の絵を描いて。」
「いいよー、君の身体は夜空みたいで、君の目は綺麗な月だね。さあ、もっと色をつけなくちゃ。真っ暗な夜空でも見失わないように。」
そうしてふたりはあるだけのマーカーペンで、風船に色を塗りたくった。そして少女は最後に残った白いスペースに言葉を添えた。
「最後に仕上げ。」
と言って少女は、切り株に置かれた沈丁花をとって、風船の紐に括りつけた。昼からずっと浮上のときを待っていた風船はいよいよ空に舞い上がろうとしていた。
「僕たちのカラフルロケットだね。」と黒猫は飛び跳ねた。
「あはは、そうだね。それじゃ、あの星に向かって、出発。」
ゆっくりと少女の手から離れたカラフルロケットは、森の中、車庫のうえに大きくひらけた空へと真っすぐ進んでいった。
ふたりは祈り、それぞれの想いをカラフルロケットと一緒に夜空に高く打ち上げた。
届け。届け。
17. 流星と風船
さすらいと犬は港にいた。ここで明日の早朝の船出を待つのだという。さすらいはある島に向かうらしい。まだ眠るには早い時間だったので、ふたりは堤防に並んで腰かけ、夜空を眺めていた。
良く晴れた夜だったので、星がいつもより多く見えるようだった。ときおり星が流れるのを見て、さすらいは言った。
「毎日夜空を眺めるんだ。流れ星っていうのが案外たくさんあるんだよな。綺麗だと思うか?」
犬にはよくわからなかった。
「実はあまり夜空をみたことがないんだ。」
「あんな森にいてか?」さすらいは笑った。
「星をみると、たくさんの目に見られているような気がする。怖くなる。」
「今も怖いか?」さすらいは犬の目を見つめて尋ねた。
「いや。」犬はさすらいの目から夜空に視線を移しながら答えた。
「そっか。でも、俺は夜空をみてると不思議に思うこともあるよ。」
そのときちょうどふたりの視界の真ん中に、長く星が流れた。少し間をおいてさすらいが言った。
「光って消える流れ星が美しいならさ、俺たちの命も美しいのかな。」
犬は黙って星空を見上げていた。
「流れ星って、星じゃないらしいんだ。宇宙の塵だかゴミだかが地球に落ちてきて、大気に触れると燃えて消えちまう。それを俺たちは星とよんでありがたがってる。」
さすらいの声からはうっすらと涙の色が読み取れた。犬はさすらいにも過去があり、これから過ごす長い時間の中で、きっとそれを知る日がくるのだろうと思った。そして、自分の過去を、大切な記憶としてさすらいに語れる日も。
「燃えるように生きろってことなのかもな。塵やゴミでも、燃える速度で進めば輝いて、光って消えて、美しい。そう思うしかないか!明日からは冒険だぞ、相棒。」
さすらいはおどけて見せて、被っていた帽子を犬の頭に乗せ、優しくギターを弾き始めた。
犬のしっぽはさすらいの音に合わせるように揺れていた。
「歌わないのか?」と犬は尋ねた。
さすらいは答えた。「言葉なんかじゃ足りないときもあるだろ?」
ふたりが座る堤防の向こう側には小高くなった丘が見え、彼らが出会った森があった。やがて森から風船がひとつ舞い上がってきた。さすらいの音色を聴きながら、ゆっくり真っすぐと飛んでいく風船が宇宙に消えるまで、犬はじっとそれを見つめていた。
18. 言葉と心
真っ黒い猫がしっぽを揺らして夜を闊歩する。月明かりが照らす暗い道を散歩する黒猫は、隣の少女と共に家路についていた。
にゃあお。大きな声で鳴くと、隣で少女が笑う。この街の夜は、何かで満ちている。
家に戻ると、忘れた携帯電話に友達から連絡が入っていた。
昨日のこと、ごめんね。ありがとう。今日学校来なかったけど、大丈夫?
少女は大きな荷物を降ろしたような安心感に包まれた。
全然大丈夫だよ。また明日ね。
と少女は返信し、しばらくベッドに横になって目を閉じていた。柔らかい笑みを浮かべた少女は世界を取り戻したような気分だった。
やがて窓を叩く音がした。少女は明るい表情でカーテンを開けた。
「開けてくれないのかと思ったよ。」と言って黒猫が入ってきた。
「ごめんね、ちょっといいことがあったら君のこと忘れちゃった。」
黒猫はにゃあといって少女に片手をぶつけた。
「あはは、冗談だよ。ところでね、君にこれをあげようと思うの。」
といって少女は森でみつけた犬の首輪を黒猫につけてやった。
「うちで飼ってあげられるかどうかはわからないんだけど、この窓からならいつでも私の部屋にきていいよ。ここを君の居場所にしない?」
黒猫は大喜びした。
「いいの?そしたらきっと僕は毎日だってくるよ!」
「毎日唐揚げってわけじゃないけど、お母さんにたくさん頼んでみるよ。」と少女は言った。黒猫は少女の腕に飛び込んで、グルルと喉を鳴らした。
「ちなみに私は」といって少女は黒猫をどけてリュックからギターのピックを取り出した。
「これをもらうことにしたの。その首輪と沈丁花と一緒に置いてあったやつ。」
彼女はスタンドに建てられたギターの弦にそのピックを挟み込んだ。
「私ね、そのワンちゃんへ届ける想いのほかに、今日は君と会えて本当に良かったって想いも、カラフルロケットに込めたんだ。」
黒猫はにゃあと嬉しそうに鳴いた。黒猫はカラフルロケットのことを考え、少女が最後に何か文字を書いていたことを思い出し、彼女に尋ねた。
「ねえ、最後にカラフルロケットなんて書いたの?」
彼らはときおり人間の言葉がわかっても、文字が読めることはないのだ。
「んー?」少女はにんまりとして黒猫を持ち上げると、首輪が緩くぶら下がった。
「ちょっと君には大きいかな?」
そういうと少女は黒猫から首輪をとって、新しく穴をあけてやった。そして首輪の裏にペンで言葉を書いてから、黒猫に返した。
黒猫は再び聞いた。「なんて書いたの?」
少女の答えを聞くと、黒猫は勢いよく少女に飛び乗った。
「わあ!」勢い余った少女はベッドに倒れたが、黒猫はそのまま少女の胸の上で丸くなってしまった。
「重いよ。」と少女は言った。黒猫は動かず、少女の顔の目の前で目を閉じた。
「なんでここで寝るの。」
「いちばん心に近いからだよ」と黒猫は言った。
「へへ、何それ。心がどこにあるのかわかるの?」
少女はおかしくて聞き返した。
「当たり前だよ、僕がいちばん安心するところに、君の心があるんだ。決まってるじゃないか。」黒猫は得意げに片目をあけて少女をみた。
少女は黒猫を撫でながら、もう一度同じ言葉を言った。
「大好き。」
おわり。
(作: 伊藤風次・ささ)