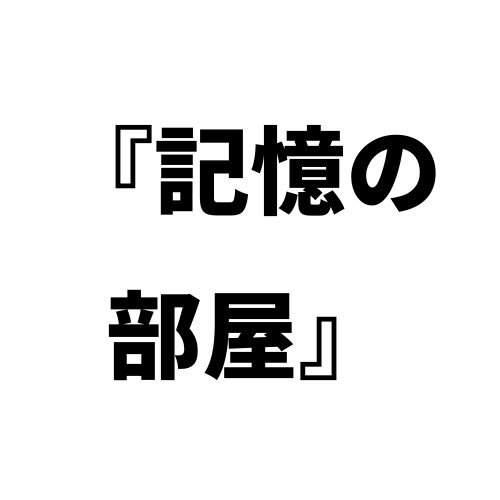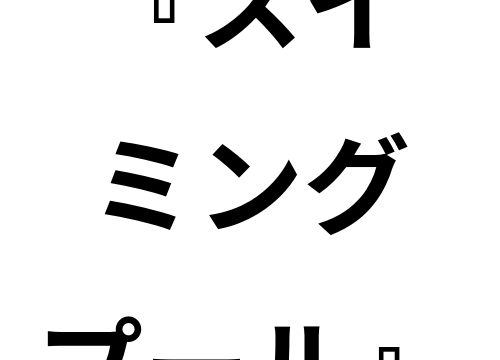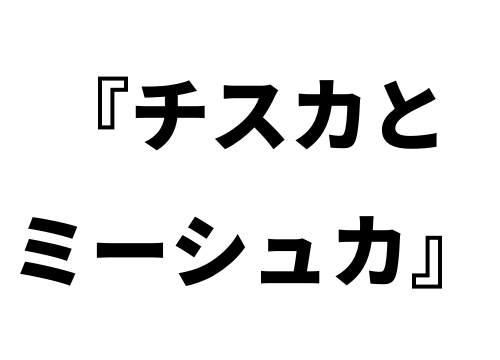灰色の部屋の真ん中に、椅子がひとつ置いてある。
どこからこの部屋に入ってきたのか覚えていないが、見渡すかぎり出入口はない。
窓もどこにも見当たらないが、別段暗いわけでもない。
無機質な立方体の真ん中にただ椅子があるだけだ。
私がそれに腰かけると、正面の壁に、昨日の映像が映し出された。
昨日の私の瞳に映った映像。瞬きと瞬きの間を埋め尽くした、美しい映像。
昨日はとても印象的な日だった。
言ってしまえば、人生のなかで、最も幸せな日のひとつだったのかもしれない。
映像に映るのは、美しい彼女の姿だ。
落ち着いた後ろ姿、優しい歩調、丁寧な声、賢い視線、細やかな仕草、包み込む笑顔。
私は繰り返される昨日の映像をただずっと眺めていた。
何度も、何度も、何度も。
この映像がすでに過去の物だという事実に胸の痛みを覚えながらも、正面の壁から目を離すことができない。
繰り返される昨日の映像は、とても正確で、見えたもののすべては映像に、聞こえたもののすべては音声に、克明に記録されていた。
しかし、昨日の記録から、匂いと温度と感触が欠落しているというおぞましい事実に気が付くまでに、それほど時間はかからなかった。
欠落した匂いはどこに漂っていったのか。
欠落した温度を記録しておく術はなかったのか。
欠落した感触はいったいどうすれば取り戻せるのか。
克明に思える昨日は、すでに昨日ではなくなり始めている。
ふと、昨日の音声が乱れた気がした。
耳をひそめてよく音声を聞くと、背景で響いていた風の音が消えている。
私は焦って、周囲を見渡した。
誰かが映像を編集しているのだろうか。
しかし、灰色の部屋は映像を見始める前とまったく変わらず、ただの立方体だった。
映写室もプロジェクターもどこにもない。この映像を流している他人もいるはずがない。
この映像はどこに保存されているのだろうと思った。保存してあるものが流されていて、それから風の音が欠落したというのなら、誰かが昨日を編集しているのかもしれない。
誰かが編集しているなら、私は編集を止めるように頼まなければならないと思った。
しかし編集者は、まったくもって見当たらず、私があたふたと探索している間に、映像からはすべての背景音が消えていた。
残ったのは、彼女の声だけだった。
彼女の声を聞いた私を思い直した。
彼女の声だけが残っていればいい。
彼女の声だけが残っているなんて、なんて素晴らしいのだろう。
そして、また椅子に深く腰掛けた。
純度を増した映像は、やがて彼女が映されているシーンのみが再生されるように変化していった。
この変化は私にとって受け入れやすいものだった。
昨日のすべてをあるがままに経験した昨日があり、その昨日を永劫回帰してしまえるならば、それ以上の望みはない。しかし、時間は回帰せずに進んでいるようだ。1秒が過ぎるたびに昨日から自分が離れていく感覚には引き裂かれるような思いをさせられている。
この灰色の部屋の映像は、その抗いがたく広がりつづける距離のことを考えないようにするためには、とても役に立つものだった。だが、匂いと温度と感触の欠落に気が付いてからは、むしろ距離のことを想起させるものと転じた。
欠落が発生し、欠落が距離ならば、私は欠落に注目するのではなく、残されたものに注目するべきだと思う。
欠落によって、残されたものは純度を増し、純度を増すたびに、より克明な昨日に肉迫できる。
映像からは彼女以外が欠落していく。
欠落によって彼女は純化されていく。
だが、私の夢想的な屁理屈もここで潰えた。
繰り返し、繰り返し、繰り返し、昨日の映像を眺めているうちに、昨日の彼女の映像はコマ送りになり、音声は途切れ途切れになりはじめた。
先ほどまでは全編流れるように見えていた世界が、彼女の絵画の連続体に変化した。
先ほどまですべての流れを追えていた彼女の発話が、いくつかの印象的な言葉のコレクションに変化した。
私は再びうろたえたが、もはや椅子から離れることはできなかった。
実際に強く離れようと意志を持ったわけではないので、もしかしたらその気になれば立ち上がれたのかもしれない。
しかし、この昨日のコマ送りが、これからさらに欠落をつづけていく運命にあることを、私は直感的に理解していたので、もはや何ひとつ見逃したくない、この上映を見続けていたいと、強く願ったのだった。
コマ送りは徐々にパラパラ漫画のような粒度にまで減ぜられた。
言葉のコレクションからは彼女の声色が薄れ、やがて意味だけを伝達するシンボルになった。
私はそれでも目を離さずに、ずっと、ずっと、繰り返しそれを見つめていた。
灰色の部屋には時間がない。
正確には時間はあるのだと思う。しかし、それを把握する術も、数える術もないので、時間という感覚がわからなくなる。
ただ、私が「昨日」と呼んだ日が欠落していくたびに、その「昨日」から私が離れていっているということだけが理解できる。この宇宙のように広がりつづけるだけで、縮まることのない距離が、ひたすら私を痛めつけるだけの空間。
どれだけの時間が経ったのか
幾度繰り返しこの上映を眺めていたのか。
気が付けば、繰り返しという形式をとることさえできないまでに、「昨日」は単純化された。
正面の壁には、数枚の彼女の絵と、いくつかの彼女の言葉だけが映し出されていた。
「昨日」から幅のある時間が欠落したのだ。
一連の流れであった「昨日」はいくつもの部分に分解され、私に強い印象を与えた部分のみが静止して並んでいるだけのものになり果てた。
それでも、私にこれらの絵画と言葉を眺めるのをやめる理由は何ひとつなかった。
人は過ぎ去った時間に近づこうとして美術館や博物館を訪れるではないか。
そうしても過去にいけるわけではないし、過去についてわかることはほんの少しだ。
それでもそこに行くことでしか、過去と近接することはできない。
私も離れつづける「昨日」に少しでも近づくためには、この椅子から離れるわけにはいかない。
ここにいることでしか、もはや「昨日」に触れることはできないのだから。
幾星霜も過ぎたような感覚がしてきたころ、色さえ失った絵画は薄らぼやけ始め、言葉は細かい言い回しに揺らぎが出始めた。
消えてしまいそうな、消えてしまいそうな彼女の姿と、
消えてしまいそうな、消えてしまいそうな彼女の言葉。
突然と、昨日が消えていくさまを受け入れらない気持ちが胸を突き上げた。
私は正面の壁から目をそらし、俯いて泣いた。
顔を覆った両手の指の隙間から見える床からは、正面の壁を反射して、「昨日」が消えていく過程が、なんの容赦もなく進行する様子が微かに感じられた。
痛い。痛い。痛い。
私が椅子の上で涙を流していると、その涙が落ちた先、足元に1本の鉛筆が転がっていた。
再び正面の壁を見やると、すべてが薄らいで消えてしまいそうな中、それでもまだ、私にはその残像から、消える前の鮮明な「昨日」の断片がはっきりと見えた。
私はしばらくぶりに椅子から立ち上がり、鉛筆を拾いあげ、正面の壁に向かった。
そして、鉛筆の先で壁に触れ、消えゆく彼女の姿と言葉を復元していった。
復元作業の最中にも、欠落は継続した。
正面の壁は、復元と欠落の追いかけっこを映し出すこととなった。
忘れたくない。忘れてたまるか。
彼女との「昨日」が完全に欠落するなど、私は絶対に許さない。
私は欠落に負けるまいと、必死になって鉛筆を動かし、「彼女」を復元した。
このような作業が、また永遠のようにつづいた。
やがて欠落は速度を緩め、もはや完全に止まったように思えた。
欠落に勝利した私は、またしばらくぶりに椅子に戻った。
久しぶりに深く腰掛けて、正面の壁を見る。
私の「昨日」は保全され、「彼女」は欠落から守られた。
私は満足して、また、ずっとずっと正面の壁を眺めていた。
欠落は完全に終わったのだ。
もうこれで、「昨日」が失われることはない。
もうこれで、「彼女」が欠落することはない。
「昨日」も「彼女」もここに永遠に存在する。
私が椅子から離れないかぎり、これ以上、広がりつづける距離に苦しむことはない。
ときどき
「はて、彼女はこんな姿だったかな」とか
「あれ、彼女はこんなことを言ったかな」とか思うことがあるが
私は気にしないことにしている。
あの終わりの見えない復元作業をこなした私だ。
その事実が、私にとって「昨日」が、「彼女」が、どれだけ大切であるかということの証明だ。
大切なものだけが、ここに純化して残っている。
私が残した宝物なのだ。
そう自分に言い聞かせながら、以来、私はこの椅子に座りつづけている。
出口のない灰色の部屋の真ん中に置かれたこの椅子に座って、
彼は正面の壁を見つめつづけている。