人生初のハンガリー小説はアゴタ・クリストフの『悪童日記』でした。
正直誰にも勧められる小説かといわれれば
二つ返事にYesとはいえませんが、気の合う友人には機会をみて推したいと思える一冊。
Contents
邦題について
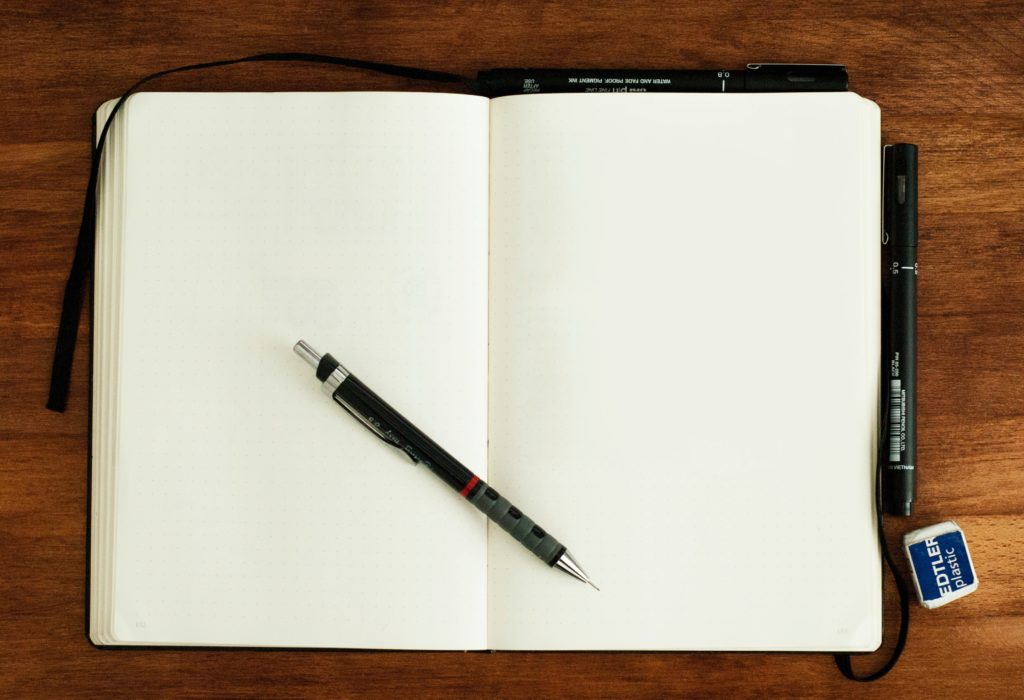
原題の『Le Grand Cahier』は「大きなノート」といった意味でしかないので
『悪童日記』というタイトルは読む前から読み手の視点を固めてしまっているようなきもしますが、この作品のたたえるおどろおどろしくも乾ききった雰囲気を表すうえで、『悪童日記』というタイトルには「まさにこれぞ」という相応しさがあります。
僕が訳者であれば、おもわずしたり顔をしたくなる邦題ですね。
この作品の主人公は戦争の疎開児童として祖母の家に預けられた双子であり、全編を通して語り手はこの双子に固定されています。
この双子はまさに悪童。
それも可愛げにある悪ガキではなく、まさに「悪」という恐ろしさとしたたかさをもっています。
浦沢直樹の『MONSTER』に出てくるヨハン・リーベルトのような恐ろしさです。
しかしこの小説にはこの双子以外にも、まともな人間がほとんど出てこないのです。
人殺しか、性的錯綜者か、権力の犬か。そしてまともな人間や弱い人間は悲惨に死んできます。
激烈卑劣な戦争下の環境において、この双子は痛みや苦しみにたえる訓練をし、生き抜くために知恵を磨き、驚きの生命力を見せます。そして同時に心は封印されていくよう。
では、果たしてこの双子を「悪童」と断定していいものなのか。
悪は人なのか環境なのか。
原題の「大きなノート」の中立性は、読者に判断の余白を残すものでした。
この邦題によって、原作の投げかけるひとつの大きな問いが、「悪童」という強烈に印象的な言葉のフィルターを通してしか届かなくなってしまっているような気が、しないでもありません。
“作文の内容は真実でなければならない”

『悪童日記』という作品の中でも最も重要な一行はこれでしょう。
”作文の内容は真実でなければならない。”
『悪童日記』アゴタ・クリストフ著 堀茂樹訳 早川書房
疎開先の貧しい社会で強く生きていくために、自分たちにさまざまなルールを課す主人公の双子。
彼らがペンとノートを手にすると、作文をつづるようになりますが、そのときに定めたルールです。
真実でなければならないというのは、単にウソや想像を書いてはいけないということではありません。
作文には、解釈や判断や感情も書いてはいけないのです。
「良い」「悪い」「嫌だ」「辛い」「優しい」「すごい」「美しい」などという表現はすべて真実ではありません。「良い」ものにも「良くない」部分があるかもしれないからです。
つまり書いて良いのは事実だけ。
「『花が綺麗』と彼女は言った」とは書けても
「花が綺麗」とは書けないということです。
そして思い出してほしいのが、この『悪童日記』という作品こそがその、主人公の双子による手記という体裁をとっているということ。
この物語は徹頭徹尾、この双子の視点に固定されているので、やはり全体を通して解釈・判断・感情という、主観が混じった描写、つまり誤謬を含む恐れのある表現が一切出てきません。
しかし、物語は戦禍のまがまがしいエログロの世界。
これがただ淡々と事実として描かれているさまが実に強烈です。
事実の羅列が、実に大きな感情的なパワーを持って僕たちに迫ってきます。
非常に逆説の利いた、文学的な力のある作品だと感じました。
だからこそ、邦題の『悪童日記』には議論の余地があるのです。
やはりそこに邦題をつけた人の解釈が一滴入ってしまっている。
『悪童日記』のほうが原題『Le Grand Cahier』の意味する「大きなノート」よりは、言葉として印象的で、小説のタイトルとしては優れているように思えます。
しかし、このような作品的特徴、それも物語を一貫する核となる特性のひとつを考慮に入れるならば、『大きなノート』というタイトルのままにしたほうが、作品も持つ力をそのタイトルにも、同じ仕組みで持たせることができたと思います。
このほどの内容を『大きなノート』と呼んでしまうアゴタ・クリストフ。
ロボットのように聞こえるこの表現が、抑圧された人間の感情を逆説的に描き出す。
むしろこの極端な抑圧を想像的に爆発させる仕事を、読者に任せてしまっているとも考えられます。
邦題については、「売れるタイトル」にしないといけないという事情もあるでしょうし、『悪童日記』というのはやはり魅力的な言葉でもあるので、一概に良い悪いということはできないのだけれど。
”名前”がない物語

もうひとつこの作品の特徴をあげるなら、名前が一切出てこないということです。
主人公の双子も名前で呼ばれることはなく、そのほかの登場人物も、独特の呼び名や職業、立場などで呼ばれるだけで、具体的な固有名詞は一切出てきません。
さらにハンガリーの首都であるブダペストを暗に示すと思われる街も「大きな街」という意味ありげな表現に伏せられ、他にも街の名前は出てきません。
戦争下の物語ではありますが、ナチスドイツやロシア軍をモデルにしているであろう軍隊や国の名前を伏せられています。
この特徴も、作者がこだわった「真実のみを書く」というルールと重ねて考えることができます。「名前」というのは、いかなる情報を伝えるものでもないからです。
「ヴィトゼンハウゼン」
・・・という名前を聞いて何か連想できるものはあるでしょうか?
実は友人のツテで僕が滞在したことのあるドイツの中心近くにある田舎の村の名前なのですが、日本ではこの名前を知る人はほとんどいないでしょう。
しかし「ここは、緑豊かな田舎で、農業系の大学近隣にあって、、、一応少し車を走らせれば駅もあって・・・」といえば少しはイメージが湧いてくる。
つまり名前というのはそれ自体では何の意味も持たないのです。
名前はいろんなイメージや特徴、さらに人名あれば自我、地名であれば文化などを入れ込むための箱に過ぎないということです。
そして箱ということは、何を中身にいれてその「名前」を理解しているかという点で、人によって揺らぎがあるということです。
さらに、箱は角度によって異なる色を持っているかも知れません。
「東京」という名前の箱に「政治経済と華やかな現代文化の中心地」「なんでも売ってる買い物が楽しい街」などポジティブなイメージを詰め込んでいる人がいます。
一方で同じ「東京」という名前の箱に「人がせわしくて冷たい冷凍都市」「モノと人であふれてごちゃごちゃうるさい疲れる街」などネガティブなイメージを詰め込んでいる人もいます。
「日本」という箱も、「アニメ」「日本食」「公共マナー」という角度からみれば素晴らしく聞こえる名前ですが、「第二次世界大戦」「長時間労働」「感情表現」という角度から見ればあまり良く聞こえる名前ではありません、
このような意味で、固有名詞というのはその他の言語表現と比べて、伝えるべき事実に揺らぎを与えやすい嫌いがあるように思えます。
作文の内容は真実でなければならない。
この命題を一気通貫つきとおしているアゴタ・クリストフが、物語から”名前”を排除した理由は、こういう部分にあるのではないでしょうか。
歴史と表現を中立化することで問うていること

固有名詞は一切出てこない『悪童日記』ですが、第二次世界大戦終戦間近のハンガリーを舞台にしていることは話の流れと作者アゴタ・クリストフの過去から明らかです。
第二次世界大戦においてハンガリーは非常に微妙な立ち位置に置かれました。当初は日独伊を中心とする枢軸国側として特にドイツとの関係を深めますが、同じく枢軸国側に接近していたユーゴスラビアがドイツとの関係を悪化させます。
これに怒ったドイツはユーゴスラビアへ侵攻しますが、その通り道にあるのがハンガリーでした。ハンガリーというマジャール人の小国はドイツとユーゴスラビアというゲルマン人とスラブ人の強国に板挟みにされる形となりました。
さらにドイツはソ連と激しく対立していたため、ハンガリーは対ソ参戦するようにドイツから圧力を受けます。しかしこの戦闘でハンガリーは大打撃を受け、ドイツとの距離感をはかりはじめました。
大戦末期になると、矢十字党というハンガリーの極右政権がクーデターで政権を獲得。ハンガリーは完全にドイツの傀儡と化します。
こうなるといよいよ国民の目線から見ると、敵はドイツかソ連かわからなくなってきます。大戦の構造上は枢軸国側なので敵はソ連(そして西部戦線ではフランスやイギリス)です。しかし、ナチスドイツと国内の傀儡政権が武力を背景に圧政を敷いているのであれば、国民にとってソ連は強権的な支配からの解放者として進軍してくるようにもみえたはずです。
『悪童日記』はこのような戦況下のハンガリーの田舎町の惨状を、ミクロの視点で描いた作品です。
惨状と言っても爆撃があるとか、悲痛な別れがあるとか、そんなドラマチックな映画でフォーカスされるようなものではありません。
盗みや性的な堕落、親子愛の喪失、軍人の脅威などが「真実の表現」のみを用いて淡々と描かれるのです。
アゴタ・クリストフが問うているのは、このようなミクロの視点で「人間」をみたときに、その「行動」について「善悪」はあるのか??ということではないでしょうか。
だからこそすべて背景から名前を消し去り、個人の解釈を消し去り、これをどう考えるか?という問いを暗示的に、それでも強烈に、僕たち読者に投げかけているのではないでしょうか。
アゴタ・クリストフが、ここまで具体的な歴史的事実を背景とした話にしたのは、この話に現実味を持たせるためだと思います。
しかしそれから名前を消し去ったのは、個々人が矢十字党やソ連やドイツやブダペストという箱に詰めているイメージを取り去り、中立化するためだと思います。
そして「真実の表現」にこだわり、文章から解釈を排しているのは、他人の意見などというフィルターを解さずに僕たちが「事実」と向き合うため。そして自分でそれについて考えるためだと思います。
まとめ:残された疑問

さて、ここまで書いてきたとおり『悪童日記』という作品は、独特は表現上のルールの妙によって僕たち読者に強く「事実」を投げかけているということでした。
しかし、この作品を通して、僕にはなぜそうしたのか、それが何を意味するのかさっぱりわからないことが1点あります。
それはなぜ主人公は双子なのかということ。
そしてこの二人が常に一緒であるということは何を暗示しているのかということ。
物語では、常に語り手は一人称で、この主人公の双子です。
使っている一人称は「ぼくら」で、双子のうちどちらが何をしたのか分けて描かれている部分はほとんどありません。
分けているにしても「ひとりはこうして」「もうひとりはこうした」といった具合で、この二人の同一性というものを分離しないで済む書き方に留められています。
ほとんどのセリフも「ぼくらは『~~~』といった」という形で書かれています。まるでスリラー映画で出てきそうな、常に同時に同じ言葉を発して二つに重なった声でこちらを圧倒してくる恐怖の双子とやらを見ているような心地の悪さがあります。
そしてこの二人は互いに離れることを特に嫌がり、二人でひとつなんだという強い確信をもって行動してます。
正直僕がこの作品を読んでいるときは、主人公が双子であることや、彼らがなぜ常に一緒なのかということには、それほど注意を払いませんでした。
しかし、これに何らかの重要性があるということに、物語の最後に気が付きました。
ネタバレになっても申し訳ないので、どういう形でかは伏せますが、この物語が終わるとき、この双子がそれぞれに別れます。
いや、「物語の最後で彼らが別れる」というよりも、「彼らが別れたから物語が終わった」という感じがするのです。
確かにこの物語がずっと双子の手記として「ぼくら」目線で書かれていたことを考えれば、彼らが別れてしまったら、手記は止まってしまう。これには納得しました。
だからこそ、主人公が双子であり二人でひとつだったということは、物語の根幹をなす重要性をはらんでいることは明らかなのですが、これがなぜなのか全然わからない。
なにか「こうではないか?」という意見がある方がいれば是非お聞かせ願いたいです。気になる。
ちなみに『悪童日記』は続編である『ふたりの証拠』と『第三の嘘』で3部作をなす作品のようで、このへんの疑問については続編を読むことで何かわかることもあるのかな、と思ったりしています。
いろいろ読みたい本が溜まりまくっているのでいつになるかわかりませんが、是非続編も読んでみたいなあ。
ちなみに『悪童日記』は1ページあたりの文字数も少ないし、セリフ多めで、難しい言葉や文章も出てこないし、300ページ弱くらいしかないので、読みさすさという点では結構オススメです。
いろいろえぐいので、そういう意味で読みやすいかと言われれば・・・あれですけど。
では、最後まで読んでくれてありがとうございました。
今後も書評は続けていきます。











