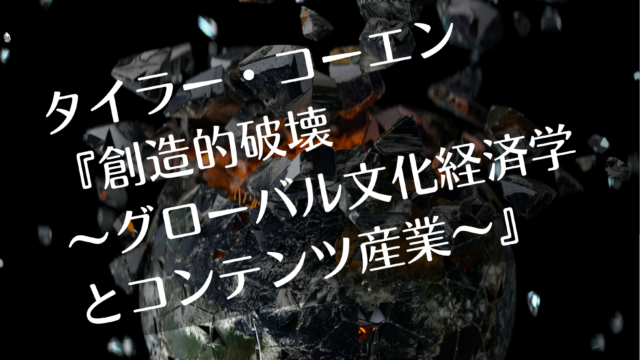知人の紹介でシュペルヴィエルの短編小説集を買った。
名前も知らない小説家だったが、短編小説集の表題にもなっている『海の上の少女』という作品がすごいのです。
なんてことない童話みたいなお話かな、でもなんとなく不思議で、わずかに不気味で、全体的に乾いたような、面白い雰囲気の作品だな。
などと思ってペラペラ読んでいたのですが。
最後の5行ほどの段落で真相が明らかになり。
僕の身体的反応、鳥肌。心理的反応、衝撃とやるせなさ。
読み終わって力が抜けました。なんかいろいろな価値観をひっくり返されたような。
そしてそのまま2周目を読み始めて、味わった。
20ページくらいしかない作品なので何周でもできる。
さて、ここまではネタバレなしで書いてきた。
ここから先は読了済みの人むけに全ネタバレで書いていくので、素で読みたい方はやめておくべし。
人生で読んだ短編小説で、ここまで食らった幕引きはジュンパ・ラリヒ『地獄/天国』と、このシュペルヴィエル『海の上の少女』だけだと思う。
まあ短編小説自体あまり数を読んでいるわけではないのですが。ちょっとこれを機に短編小説をディグるのも良いかな。
あらすじ
海の上の島にひとりで住む少女がいる。
彼女の生活は、毎日同じことの繰り返し。誰かの写真があるが、写っているのが誰かはわからない。
なぜか食料は必要な分だけ毎日棚に入っている。
勉強もする。自分で問題集を解く。
島から遠くに船舶が見えた。少女は思わず叫んでいた。
「助けて!!」
どうしてそう叫んだのかわからない。
ただ、この島から出たいと思った。
少女は年をとらない。変わらない生活が続く。
終わりがないことを気の毒に思ったは、島を取り巻く波だった。
波は、自分の力で彼女の人生を終わりにしてあげようと思う。
波は少女をさらった。
高波となって何度も少女を水に叩きつけた。
しかし、少女は傷つかなず、息絶えることはなかった。
さて、この少女はいったい誰か?
写真の中の男。
彼は船乗りであり、昔に海難事故で娘を亡くした。
この島があるこの場所で。
亡くなった少女を想う船乗りの心。
彼女に執着するその想い。
それが、この海の上の少女という、どうしようもなく、救いようのない存在を生み出してしまったのであった。
もし、そんな存在を生み出すことを望まないなら、死者のことをいつまでも思うのは、どうか止しておくことだ。
死者を想うとは
なんとも衝撃的な終わり方です。
そして一般的に受け入れられている死者に対する適切な心の向け方とはまったく異なる提言がなされる。
死者を想うことと、死者に執着することはもしかしたら別かもしれない。
しかし、シュペルヴィエルがそれを区別して書いているかどうかはこの作品からでは判断できない。
他にもシュペルヴィエルの作品には、「死」というテーマを幻想的なアイデアで包んで扱っているものがあるので、全体的なシュペルヴィエル論に話を広げれば、あるいは何か判断が下せるだろう。
残念ながら僕はそれほどシュペルヴィエルの他作品には明るくないのだけれど。
よってここでは死者を想うことと死者に執着することは区別しない。
そもそもその区別は「良い想い方」と「悪い想い方」の区別と同義になる気がする。
死者について考えるとき、どうしても遺された側は、忘れていくことを薄情だと思ってしまう。
しかし、忘却には抗えない。
死と向き合った時の絶望や悲しみは、時の流れに浄化されていく。
いずれは命日など形式的な機会や、個人的な思い出を引き出すトリガーになるような事物に触れたときにだけ、死者を思い出すようになる。
そして思い出される死者の”生者としての新鮮さ”は、時と共に失われていく。
別れから1年くらいは、まるで生きているように死者のことが思い出せる。
「もしここにいたら何と言うのだろう」という想像は、まったく自然に行われる。
むしろ、もう生きていないのだという事実のほうが、よほど非現実的に思える。
しかし3年も経つと、徐々に想像は想像でしかないように思われてくる。
死者がどのような人間だったのか、自信がなくなってきて、自分が好き勝手に補完した死者の似姿を動かしているだけなのではないかという気さえしてくる。
これはなんと残酷なことだろうと、直感的には思ってしまう。
失った悲しみさえ、ただの”反応”に過ぎなかったのではないか。
これは僕が実際に親友を亡くしてから今まで(約3年半が経過した)に体験した心の動き。
でも、実は自分の中の理性的な部分を働かせると、この忘却は「正常」なものだとすぐに理解できる。
もし別れた直後の状態が僕の中で永続したら、それこそ生きていくなんてどころの話ではない。
とはいえ、やっぱり薄情な気もする。
だから命日とか月命日はちゃんと意識する。
でも意識するために意識しているだけ。本当じゃない。僕の中で彼はどんどん小さくなる。
それでもどうにか、彼が僕に残した価値観や生き様、彼から受けた影響が僕の人生に与えている良い作用を考えて、やっぱり彼という人間が僕の中にきちんと統合されているという事実を確かめる。
このような死者との精神的な営みを続けていた僕の心に投下された爆弾が『海の上の少女』だった。
なんだこの最後の段落は。
忘れたほうがいいのか。
死者のことを想い続けることで、死者は生でも死でもない世界に閉じ込められてしまうのか。
この解釈は、まったくもって考えもしないものだった。
結局は僕は、「生きている自分」の視点から死者のことを想っていただけだったのかもしれない。
死者の視点から世界を想像すると、どうしても生前関わりがあった人を見守ったりとか、反対に恨んで憑りついたりということが思い浮かぶ。
しかし、実際に死ぬということは、存在が消えることだ。
肉体も、精神も消えてなくなる。
ただ、もしそれが中途半端に、”存在”として繋ぎ止められてしまったらどうなる?
もし、繋ぎ止めるということが、生者の執着のよってなされることだったら?
そんなことがあるのなら、まさに『海の上の少女』で描かれる少女の顛末にようになるのだろうと、素直に腹落ちする。
肉体的な進行(成長・老化)は存在しない。生でも死でもない存在。
精神的な同一性(記憶・意志)は存在しない。ただ存在して繰り返す。
ふと、亡くなった親友が最後に遺した言葉を思い出した。
「全部流してくれれば助かる」
これは彼が生前に遺した言葉に過ぎないので、死者の言葉ではない。
死という人生の一大転換点を経て、死者としての彼がまだ同じことを言うかどうかなんてわからない。
しかし、死に限りなく近いところにいた生者の言葉だ。
もちろんシュペルヴィエルの書いた小説も、所詮は生者の言葉の羅列に過ぎない。
それでも、フィクションの中で死と向き合った人間と、本当に自分の死と向き合った人間の言葉が相似しているのだから、それはどうしても説得力をもって響いてくる。
「全部流してくれれば助かる」とかも、よくある「死にたい」とかと同じで、本心ではないんじゃないの?
遺される人のことを想って気にしないように言っていただけでしょ。
素直になれないだけで本当は忘れないでほしいんだよ。助けてほしいんだよ。
とまあ、ありがちな反論がすぐに思い浮かぶ。
僕はこれらの反論は大いに的を射ていると思う。実際、これをしないといけないとも思う。
一方で、これは生の讃美歌を謳う生者の論理でしかない。
遺される者が救われる、あるいは整合性をもって不条理を解するための美談だ。
死に絡めとられ、死という状態しか選択できなくなったとき、僕たちはどのように論理をすり替えてその状態を受け入れるのだろうか。
そこにはきっと、僕たちが想像することしかできない、いや。
想像することさえできない死者の論理、あるいは死者の美談があるのかもしれない。
決して死を美化するつもりはない。生者は生者の論理で生きるべきだ。
それでも、シュペルヴィエルが提示した、生者ではなく死者から見た「生者の死者への執着が生み出すもの」は僕にとって恐ろしく新しかった。
そっちの角度から、死者への想いを否定することができるのか、と。
”きっと死者はこう思っているから供養しなくちゃ。”
そういう一見自然に思える慣習的な考え方にさえ、生者の利己的な論理が内包されている恐れがある。
手前勝手に死者の在り方を押し付けているだけなのかもしれない。
そんな考え方もできるのだなあ。
「葬式は故人ではなく、遺族のために執り行うものだ。死者にとっては別にどっちでも変わらない、死んでるんだから。でも遺族は死を整理しないといけない。同時に、それとあまりに純粋に長時間向き合わなくていいように、葬式などの儀礼、知人らへの連絡などで、心を忙しくしておくほうがいい。」
どこかでこのような話も聞いたことがある。
実体験として腑に落ちる部分がある。
いろいろ終わって落ち着くことには、死という出来事は時間的な隔たりの向こうにある。そのほうがいくぶん相応しい状態で死と向き合えるというものかもしれない。
ずいぶんシュペルヴィエルの短編小説の感想としては飛躍が過ぎるかもしれないが。。。
『海の上の少女』を読んで思ったことをつらつらと書いてみた。